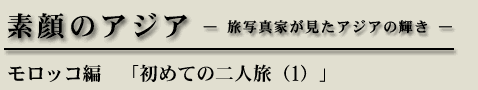|
 |
|
|
|
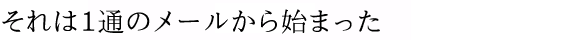 |
|
 |
|
|
 |
3ヶ月ものあいだアジアの国々を巡っていた僕が、急に北アフリカのモロッコに飛ぶことになったのは、ウィリアムという名前の日本在住のアメリカ人から届いた1通のメールがきっかけだった。
そのメールには、「私たちは新しい雑誌を立ち上げようとしています。第1号の特集はモロッコを予定しているのですが、その取材旅行に同行してくれるフォトグラファーを探しています。出発は今から2週間後なのですが、もし予定が空いているなら、すぐに連絡してください」と書かれていた(ウィリアム自身は日本語の読み書きはできないので、日本人の奥さんが代筆していた)。
2週間後というのはずいぶん急な話だと思ったが、どうやら一緒に組む予定だったフォトグラファーが急遽参加できなくなり、慌てて代わりを探す中で僕の存在を知り、急いでメールを送ってきたということのようだった。
僕はさっそく日本に国際電話をかけ(そのとき僕はバンコクにいた)、ウィリアムと奥さんと話をして、モロッコ行きを決めた。相手の素性も仕事の内容もよくわからなかったが、どうせこの先の旅の予定は白紙だったし、たまには誰かと一緒に旅をしてみるのも悪くないなと思ったのだ。
それから僕は津波の被災地を訪れるためにインドネシアのスマトラ島へ向かい、2週間後に日本から飛んできたウィリアムとバンコクで合流して、モロッコへ向かった。
|
 |
|
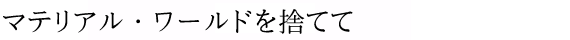 |
|
|
ウィリアムは大柄でエネルギッシュな男だった。身長は185cmほどあり、趣味のフリークライミングで鍛え上げられた体には、余分な脂肪は一切付いていなかった。年齢は39歳ということだったが、それよりも5歳は若く見えた。
僕らのコミュニケーションは全て英語だったが、彼の英語がとても聞き取りやすかったので、聞き取りに限ればあまり問題はなかった。彼は長年日本で英語教師をしているので、日本人が聞き取りやすい英語を話すことに慣れているのである。
僕らはバンコクからドバイに飛び、そこでモロッコのカサブランカ行きの飛行機に乗り換えた。飛行機に乗っている時間だけでも15時間を超える長い移動だったが、退屈には感じなかった。初対面の僕らには、話すべき話題がいくらでもあったからだ。
ウィリアムは30歳になるまでロサンゼルスに住んでいたのだが、あるとき急に旅に出ることを思い立ち、仕事を辞めて、アジア各地を何年も放浪したという。
「LAに住んでいた頃は、最高にクールな車に乗っていたんだ」と彼は言った。「その車で街を走っていると、道行く人がみんな振り返ったものだよ。とても珍しいクラシックカーでね、アメリカでは売ってないレアものさ。僕は広いアパートメントに住み、最高に綺麗なガールフレンドと付き合っていた。僕は当時プロスポーツ選手なんかをケアする理学療法士をしていたんだ。怪我をしたり故障した選手の回復を助け、リハビリを行うのが僕の仕事だった。やりがいはあったけど、とてもハードだった。クライアントは精神的に落ち込んでいるし、焦ってもいる。それをサポートしなきゃいけないからね。とにかく疲れる仕事だった」
「だから旅に出たのかい?」
「うん。でもそれだけじゃない。僕は自分が住んでいるマテリアル・ワールドにとことんうんざりしたんだよ。僕のクライアントはリッチな人ばかりだった。彼らは何百万ドルもする豪邸に住んで、何十万ドルもする高級車に乗っている。でも全然幸せそうじゃなかった。物質的な欲望には際限がないんだ。『もっと広い家を。もっと高い車を』ってね。そんな彼らの姿は、僕の未来の姿でもあった。僕だって、そのマテリアル・ワールドにどっぷり浸かっていたわけだから。だから僕は全てを捨てて、旅に出ることにしたんだ。今まで持っていたものを全部売り払ってね。バックパックひとつに全てを詰め込んだんだ」
「後悔はしていないの?」と僕は訊ねた。
「もちろん、これで良かったと思っているよ。あのとき全てを手放すことで、僕は素晴らしいものを手に入れることができたんだから、全く後悔はない。でも大抵の人は、一度自分が手にしたものを手放そうとはしない。リッチになればなるほど、よりお金に執着するようになる。特に貧しさからはい上がって豊かになった黒人には、そういう傾向が強いね。僕はアジアを旅している黒人に会ったことがほとんどないんだ。君はどう?」
「確かにあまり記憶にないな」
と僕は言った。アジアを旅するあいだ、ウィリアムのような黒人のバックパッカーを見かけたことはほとんどなかった。そもそもアジアを旅するアメリカ人自体が少数派なのである。
「そうなんだ。アメリカ人は自分たちのマテリアル・ワールドにしか関心がない。アジアの貧しい国のことなんて眼中にないんだ。アメリカの若者が関心を示すことといったら、新しいファッション、ハリウッド映画、プロスポーツ、そんなことばかりだよ。マスコミがそういう風に仕向けているんだ」
「このあいだ、あるカナダ人に聞いたんだけど、ブッシュは大統領になる前までパスポートを持っていなかったんだって。それって本当のこと?」
「どうだろう? 信じられない話だけど、ブッシュならあり得るかもね。ほんと、それくらいアメリカ人って外国に興味がないんだ」
ウィリアムによれば、アメリカ人が外国旅行をしたがらないのは、アメリカが広すぎるからでもあるという。アメリカにはナイアガラの滝があり、グランドキャニオンやイエローストーン国立公園がある。中西部に行けば、荒涼たる砂漠が広がっている。雄大な景観には不足しない国なのだ。
「たいていのアメリカ人は国内を旅するだけで満足しているんだ。わざわざモロッコまで行ってサハラ砂漠を見る必要なんてない。砂漠が見たければネバダ州に行けばいいと思っているんだよ」
「でも君は違ったんだね?」
「そうだね。僕は普通のアメリカ人よりも外の世界に対する興味が強いのかもしれない。アメリカ人は損をしていると思うよ。世界一の金持ちで、その気になればいくらでも旅ができるのに、外に出ようとしないなんてね」
何年もアジアを放浪していたウィリアムが日本に移り住むことをしたのは、タイにいるときに出会った日本人女性と結婚することに決めたからだった。二人のあいだに生まれてくる子供は、日本で育てるべきだと考えたのだ。
日本に定住するようになって5年間、彼は私立高校の英語教師をして生計を立ててきた。そのあいだに、二人の男の子の父親にもなった。
「教師の仕事にはやりがいを感じているし、収入も安定している。でも僕には世界中を旅して暮らしていた日々が忘れられなかった。このまま日本で英語教師をしながら一生を過ごしたいとは思わなかったんだ。だけど今の僕には養うべき家族がいる。自由に旅をするわけにはいかない。だから旅を仕事にする方法を考えたんだ」
「それがこのプロジェクトなんだね?」
「その通りだ」と彼は頷いた。そして、新しい英語学習雑誌を立ち上げるという自らのアイデアを熱っぽく語った。
「このプロジェクトの最も重要なコンセプトは『コミュニケーション』なんだ。日本の本屋には英語学習雑誌がたくさん並んでいるけれど、はっきり言ってつまらないものばかりだ。試験には向いているかもしれないけど、雑誌としては面白くない。僕が作りたいのは、生きた英語が学べる雑誌なんだ。読者が『私も世界中の人と会話したい』と思えるようなテキストなんだ。そのために僕らは旅をする。旅先で出会った人とコミュニケーションを取り、インタビューを行う。それを元にして雑誌を作り上げるつもりなんだ」
とても面白いアイデアだと思った。もしそんな雑誌があれば、きっと僕も買ってみるだろう。
しかし、どれほどアイデアが秀逸でも、それが必ず実現するとは限らない。彼が語るアイデアはまだ夢の段階であり、なにひとつ具体化してはいないのだ。「絵に描いた餅」に終わる可能性だって十分にあった。
「失敗する可能性は考えていない。そんなこと考えたって無駄だからね。どうやってこのプロジェクトを成功させるか、それだけが重要なんだ。僕はこの1年のあいだ、ずっとこの時が来るのを待っていたんだ。きっといい旅になる。僕はそう信じているよ」
とにかくポジティブな男だというのが、ウィリアムの第一印象だった。そしてその印象は、この1ヶ月のあいだ少しも変わることがなかった。
彼のポジティブさは困難な状況に陥ったときにこそ発揮された。もしそれがなかったら、僕らの旅はずっと厳しいものになったに違いない。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| マラケシュで出会ったオーストラリア人とイギリス人のカップル。ファンキーな格好がよく似合っていた。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|