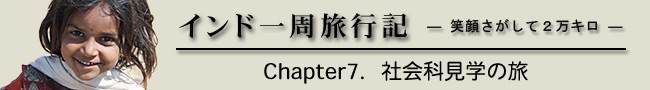|
 |
|
|
 |
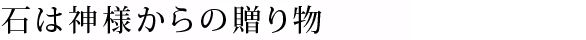 |
 |
 |
マダナパーリが「トマトの町」なら、ベタムチェッラは「大理石の町」ということになるだろう。この町の周辺にはいくつもの石切場があり、そこから産出した大理石によって町が潤っているのである。
大理石といっても、ここで採れる石はそれほど高級なものではない。研磨すれば表面がツルツルになり、見栄えがいいので家屋の床材として使われているが、値段はあまり高くないという。
「だいたい1平方メートルあたり10ドルぐらいだね。お買い得だと思うよ。あなたもお土産にひとつ買っていったらどうかね?」
と冗談めかして言ったのは、石材加工会社の社長ジャナルダナさんである。石材置き場をうろうろと歩いていた僕に、流暢な英語で声を掛けてきて、お茶をご馳走してくれたのだ。インド人のお金持ちの中には、僕のような得体の知れないバックパッカー風情を見下すような態度をとる人が少なくないのだが(本人にそんなつもりはないのかもしれないが、そのように見えてしまうのだ)、彼にはそういうところが少しもなく、フレンドリーかつ紳士的だった。
「石は神様からの贈り物だよ」とジャナルダナさんは言う。「我々は地中に埋まっている石を掘り出して磨き上げる。それを他の町へと運ぶ。いい商売だ。資源が枯渇しないかって? そんな心配はいらないよ。少なく見積もっても、あと5000年は掘り続けられるよ。まぁ私が生きているあいだは問題ないね」
彼の会社では床材だけではなく、大理石のテーブルや椅子なども作って販売している。彼は経営を多角化して成功した有能なビジネスマンなのだ。
「景気はいいよ。床石は日本のナゴヤにも輸出しているんだ。もちろん日本のお客さんにも満足してもらっているよ。インド国内のマーケットも拡大している。インド経済は毎年8%もの成長を続けているんだ。今では中流以下の家庭でも、うちの大理石を床に敷くようになっている。以前には考えられなかったことさ」
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| マッチ工場で働く女性たち。50本入りのマッチは1箱75パイサ(約2円)。この安さは農村の安い労働力によって支えられている。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
ジャナルダナさんが言うように、インド経済が急速に拡大しているのは確かである。しかし、その恩恵を受けているのは都市部周辺だけで、大多数の農村は相変わらず貧しい暮らしから抜け出せないでいるのも事実だ。
たとえば綿花はインド各地で栽培されている主要作物のひとつだが、そこで収穫作業を行う人々の賃金は驚くほど安かった。一日中働きづめで、手にできるのはわずかに30ルピー(80円)。あまりにも安いので、何かの間違いではないかと聞き直したのだが、確かに30ルピーだという。
「彼らは収穫の時期になると地主から仕事を請け負って働く季節労働者です。綿花1キロあたりの値段は20ルピーですが、労働者に支払われるのは1キロあたり2ルピーです。一日で集められるのは15キロが限度ですから、30ルピーという計算になります。安いと思いますか? でも仕方ないですよ。昔はもっと安かったんです」
そう教えてくれたのは、自身も季節労働者であるクリシュナ君だった。
「一日30ルピーで暮らすのは大変です。だから僕は他にもふたつの仕事をかけ持ちしています。村の薬剤師と塾の先生です。ひとつの仕事だけで食べていけるのは、一部の人だけなんですよ」
クリシュナ君と一緒に綿花畑をぶらぶらと歩いていると、面白い光景に出くわした。綿花を収穫する女のそばに、一羽のクジャクが寄り添っていたのである。綿花畑にクジャクがいる。そだけでも十分奇妙な光景だったが、さらに驚いたことに、女が摘み取ったばかりの綿花をクジャクの口元に差し出すと、クジャクがその綿花をパクッとついばんだのである。
「クジャクの好物が綿花だなんて知らなかったよ」と僕は言った。
「いや、僕も知らなかったですね」とクリシュナ君は首を捻った。「美味しいとは思えないんだけどな」
ということは、このクジャクは綿花畑で飼い慣らされるうちに綿花の味を覚えたのだろうか。
「このクジャクは何のために飼われているんだろう。食用なのかな?」
「いいえ、違うと思います。ペットなんでしょう。きれいな鳥ですから」
白い綿帽子の続く綿花畑と、艶やかな羽根を持つクジャク。そのクジャクに綿花を食べさせている女。この不思議な組み合わせをひとつのフレームに収めようと、僕はカメラを構えてファンダーを覗いた。
|
|
|
|
|
|
|