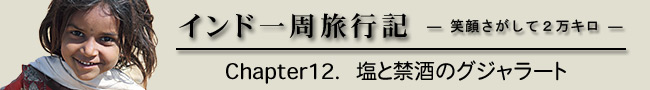|
 |
|
|
 |
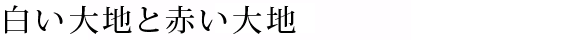 |
 |
 |
グジャラート州西部に広がるカッチ湿地は、一面真っ白い塩で覆われていた。雨季になると分厚い泥に覆われた湿地帯になるのだが、乾季には水がすっかり干上って「塩の大地」と化してしまうのだ。
カッチ湿地周辺には、当然のことながら大規模な塩田がいくつもあった。日差しは一年を通して強く、海から吹きつける風は強く、しかも遠浅の干潟が続く。これほど塩作りに適した土地は世界でも珍しいだろう。
国道沿いに並ぶ巨大な塩の山は壮観だった。人口が11億もいれば、塩の需要も莫大なものになる。人は塩なしには生きていけないのだ。
試しに計算してみよう。成人一人あたりの塩分摂取量を10gとすると、1年で3.65kgになる。これに11億をかけると402万トン。東京ドームだと1.5杯分である。なかなかイメージしにくいが、とにかくすさまじい量である。
カッチ湿地での塩作りは、僕がこれまでに訪れたアジアの塩田とは違って機械化が進んでいた。パワーショベル(日立製が多いので「ヒタチ」と呼ばれている)を使って地面の塩をごそっと掘り、それをトラクターの荷台にどさっと積み上げていくのだ。地面の泥が多少混じっていても気にしない。ごそっ、どさっ、ごそっ、どさっ、の繰り返し。なんとも豪快だった。
もっともすべての塩田が大型機械を使っているわけではなく、中小規模の塩田はいまだに人の手に頼っているところも多かった。
「今のところ人を使った方が安上がりなんです。パワーショベルはとても高価ですから」
と言うのはサリーム君。塩田オーナーの息子で、眼鏡をかけたインテリ風の若者である。彼の塩田では70人の労働者を雇っているのだが、それでもパワーショベル1台分の働きにはかなわないという。
「将来的にはもっと塩田を広げて、機械化を進めるつもりです。でもそのためには1500万ルピー(3000万円)以上の投資が必要なんです」
サリーム君の父親はもともと土地を持たない貧しい農民だった。しかし30年前に転機が訪れた。近くに大規模な化学工場が建設されたことをきっかけに、塩作りを始めたのだ。苛性ソーダなどの化学製品には塩を原料にするものが多いので、塩の需要が増えるだろうと予測したのだ。塩田は干潟だった土地に堤防を築き、海から切り離して作った。とれた塩を売り、その収入を塩田の拡大のために再投資する。それを毎年繰り返した結果、今では2.5平方キロメートルの塩田で1年に7万トンの塩を作るまでになったのである。
このようなサクセスストーリーはインドでは珍しい。大昔から続く身分制度に縛られ、社会的な流動性に乏しいインドでは、「お金持ちがもっとリッチになる」という話ならよく聞くのだが、貧農だった人が新しいビジネスで成功するという話は非常に少ないのだ。
「塩ビジネスも簡単ではありませんよ」とサリーム君は言う。「最近、塩の値段が下がってきたので、塩田をやめる人も出てきたんです。塩1トンあたりの取引価格は700から800ルピーというところです。規模を広げないとビジネスが成り立たないんです」
カッチ湿地にある塩田の中でもとりわけ印象的だったのが、ドゥワルカという町の近くにある「赤い塩田」だった。目の錯覚ではない。光の反射作用でもない。塩田に張られた水自体がインクを流したように真っ赤に染まっていたのだ。
以前、南米ボリビアのウユニ塩湖を特集したテレビ番組で、同じように赤い色をした湖のことを取り上げていた。湖の水が赤い理由は特殊なプランクトンが含まれているからで、フラミンゴが鮮やかなピンク色をしているのもそのプランクトンを食べているからだ、という話だった。これは後で知ったことだが、実はカッチ湿地もフラミンゴの生息地のひとつになっているそうだ。ということは、この赤い水の正体もプランクトンだと考えていいだろう。
塩田はおそろしく静かだった。風が吹き抜ける音と、その風が水面に立てるさざ波の音。それだけしか聞こえない。
僕は積み上げられた塩の山に登って、見渡す限り真っ赤に染まった世界を眺めた。
それは現実離れした奇妙な光景だった。
地球がまだ熱かった頃、「生命のスープ」と呼ばれる原始の海が広がる世界に迷い込んだ気がした。
|
|
|
|
|
|
|