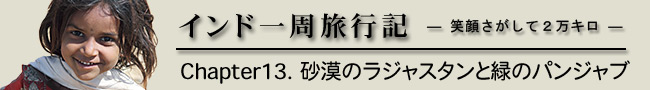|
 |
|
|
 |
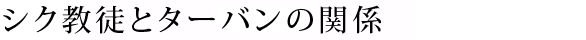 |
 |
 |
シク教徒を象徴するものと言えば「ターバン」と「髭」だが、それが若い世代からは敬遠されはじめているという。マンディップ君とカレッジの友達も誰一人としてターバンを巻いていなかったし、短髪で髭も剃っていた。正式なシク教徒は髪や髭を「神から与えられたもの」として決して切らないのだが、そのような古い掟を忠実に守っている若者はすでに少数派になっているようだ。本来は飲酒も禁じられているのだが、今ではむしろ酒に寛容な地域であることは、すでに書いた通りだ。
「僕らの父親の世代はみんなターバンを巻いています。祖父たちが強制したからです。ターバンを巻かないと殴られたんです。でも僕の父親は『お前の好きなようにしろ』と言ってくれました。だから僕は自分の意志でターバンを巻かないと決めたんです。あれを巻いていると頭が痛くなるし、重たくて邪魔だからです。それに夏になるととても暑い」
「でもターバンを巻いている人たちは暑そうに見えないけど」
「我慢しているんです。それに何十年もずっと巻いていたら、暑さにも慣れますよ」
外部の人間、特に僕のように写真を撮る者にとって、シク教徒のターバン姿は実に格好いいし、ぜひとも残して欲しい習慣である。でも実際に巻いている人にしかわからない苦労も多いのだろう。「やせ我慢」が評価された時代もあったのかもしれない。実利よりも伝統を重んじる時代もあったのかもしれない。でも今は違う。個人の選択の幅が増え、伝統衣装は次第に廃れていく。
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 葬式のために正装をして集まったシク教徒の男たち。色とりどりのターバンと立派なヒゲ、白いシャツがとてもきまっている。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
日本人がまさにそうだ。ちょんまげを切ったのは100年以上も前だし、浴衣や結婚式などを除いて普段着として和服を着ることはまずない。こうした世界的な「ドレス・ダウン」の流れは、インドにも確実に波及しているのだ。
とはいえ頭にターバンを巻いたシク教徒が、日本人にとってもっとも「インド人らしいイメージ」であることは今でも変わらない。実際のところ、シク教徒がインド人全体に占める割合はわずか2%足らず。圧倒的なマイノリティーなのだが、そんな彼らが外国で「インド人の代名詞」のように扱われるのは、シク教徒が海外志向、つまり「外国で一旗揚げてやろうじゃないか」という強い意志を持っているからである。一説によれば、海外に定住しているインド人の3分の1がシク教徒で占められているという。
マンディップ君も来月からニュージーランドに留学する予定だ。留学先にニュージーランドを選んだのは、すでに彼の親戚が何人も住んでいるから。ビザを取得するためには銀行口座の残高が80万ルピー(160万円)以上あることを証明しなければいけないので、そのために長期のローンを組んだ。英語も熱心に勉強してきたので、ボキャブラリーは僕よりもはるかに豊富だった。
「僕はこの国が好きじゃありません」とマンディップ君は言った。「自分の村は好きです。でもインドという国とインド政府は嫌いです。政府はシク教徒を差別してきました。シク教徒である限り、良い仕事に就くことはできないんです。この国のシステムはフェアではありません」
「でも今の首相はシク教徒だよね?」
「マンモハン・シン首相は立派な人です。とても頭が良い。しかし彼は操り人形でしかない。実権はソニア・ガンディーが握っています。みんなが知っていることです」
「君はずっと外国で暮らすつもりなの?」
「そうです。外国で仕事を見つけて、できれば永住権を取りたいと思っています。インドに戻ってくるつもりはありません」
海外を目指すシク教徒の全員が、マンディップ君のように強い覚悟を持っているわけではないだろう。「若い頃だけ外国で働いて、あとは故郷に戻って店でも開いて、のんびり暮らそう」と考えている人だって多いはずだ(実際、そういうルートを辿ったシク教徒のおじさんに会ったこともある)。
けれども、マンディップ君のように「故郷を捨てる」ぐらいの決意で臨まないことには、異国の地での成功がおぼつかないのも確かだ。言葉の壁や文化の壁、外国人に対する差別を乗り越えてのし上がるのは、生半可なことではない。それは世界各地に散らばった華僑や、南米に渡った日本人移民の例を見てもよくわかる。
そうやって海外に出たシク教徒たちが稼いだ外貨は、パンジャブ州の経済にとって必要不可欠なものになっている。「トヨタのない名古屋」や「観光客のいないカトマンズ」が考えられないように、パンジャブ州の経済は海外からの送金なしには成り立たないのだ。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| パンジャブ州ムクトサールのナイトマーケット。野菜や果物をガス灯の明かりの元で売っている。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
たとえばそれは場違いなほど立派な結婚式場を見ればよくわかる。パンジャブ州にはあちこちに広くて豪華な結婚式場があるのだが、それらは外国で働くシク教徒たちの結婚式のために建てられたものなのだ。
モガという町の郊外にある「マジェスティック・リゾート」はそうした結婚式場の中でももっとも洗練されたもののひとつだ。ピカピカに磨き込まれたガラス張りのエントランスホールと、パラソルが並んだ屋外のパーティースペース。丁寧に刈り込まれた植木が配置された広大な芝生の庭。名前の通りリゾートホテルのような外観だが、もちろん周囲に海はなく、観光地もなかった。
オーナーであるジョギさんによると、この式場がオープンしたのは5年前のこと。主に北米やオーストラリアなどで働いているパンジャブ人が顧客だという。インドでは親が見つけた相手と結婚する「アレンジ婚」が普通なので、たとえ外国で働いている人でも、結婚式は故郷に戻って行うのだ。
インドの結婚式が盛大なのはよく知られているが、ここで行われる結婚式もだいたい300人から400人もの招待客が集まるという。費用は30万ルピー(60万円)から40万ルピー(80万円)程度だが、中には100万ルピーを超えることもあるそうだ。インド人の年収を考えると、これは相当な額である。ちなみに結婚にかかる費用は、新婦の親が支払うことになっている。悪名高いダウリ(花嫁持参金)は最近になってずいぶん減ってきたものの、娘を持つ親の負担は以前とあまり変わっていないようだ。
|
|
|
|
|
|
|