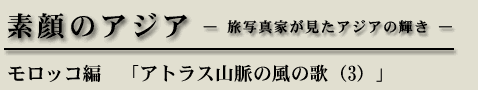|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
アトラス山脈の山村を歩く間に、僕らは何人かの若者に話を聞くことができた。
一人は遊牧民の家族の長男だった。その一家は雨風をしのげる洞窟の中に住みながら、羊や山羊を放牧して暮らしていた。360度どこを見渡しても、荒れた大地と茶色く乾いた草と羊以外には何も見えないようなところだった。このような辺境に住めるのはタフな遊牧民以外にはいないだろう。
その16歳の長男の仕事は、羊の群れを統率することだった。伝統衣装ジェラバに身を包み、頭には黒い布を巻いていた。彼と弟は投石機を使って、遠く離れた羊の近くに石ころを飛ばし、群れからはぐれそうになった羊を上手にコントロールしていた。
投石機といっても、羊の毛で編んだ細いマフラー状の布に石ころを挟んでブンブンと振り回すだけの原始的な代物なのだが、彼らはそれを使って200mも先に石ころを飛ばすことができた。僕もトライしてみたのだが、リリースのタイミングがなかなか難しく、初めてクラブを握ったゴルファーみたいに石ころはあさっての方向にばかり飛んでいった。
代々羊飼いをやっている家に生まれた若者にとっても、この土地での暮らしは過酷なようだった。「本音を言えば他の土地に行って働きたいんです」と彼は告白した。肉体労働でも何でもいいから、町へ出て現金収入を得たい。そうすれば今よりもいい生活が送れるはずだ、と。
彼は丘の上に立って羊の群れを見下ろしている。彼はときどき口笛を吹いたり石を投げたりして、群れを動かしていく。時間は彼の前であくまでもゆっくりと流れていく。その流れは好奇心旺盛な若者には耐え難いほど遅いのかもしれない。
彼はいつの日か投石機を置いて、町に出て行くのだろうか。それとも父や祖父がそうしたように、ここに留まり続けるのだろうか。その答えはきっと彼自身しか知らないのだろう。
|
 |
|
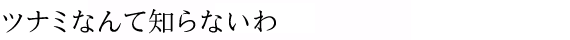 |
|
|
二十歳の女の子サディアとは、休憩を取るために立ち寄った家で出会った。彼女の家は数軒の家が集まる集落の端にあった。集落には電気はなく、テレビもラジオもなかった。外の人間が通ることもほとんどないという。「陸の孤島」という形容詞がぴったりと来るような場所だった。
「暇な時間は家族とお喋りをして過ごしているんです」と彼女は言った。
「どんなことを話しているの?」
「雨が降るか降らないか。それが一番の関心事です」
とサディアは言った。雨が降れば草が多く生え、羊たちも肥え太ることができるが、雨が降らない時期(どうやら一年の大半がそうらしいのだが)が長く続くと、たちまち生活が困窮してしまうという。
水が死活問題であるのは、この集落に限ったことではなかった。ここを訪れる前に立ち寄った村では、同じ川を利用するふたつの村同士がトラブルを起こしていた。川の下流に位置する村の住民が、上流の村人に対して、「お前の村が水を無駄に使っているから、我々に十分な水が回ってこない」と主張するのだが、上流の方はそれを認めようとしないというのである。
ふたつの村は以前から水を巡って対立しており、時には暴力沙汰にまで発展することもあるらしい。モロッコには植民地時代にヨーロッパから導入された近代的な法律と、イスラム法と、古くからある地域的な慣習という三つの法が存在しているのだが、水利権を巡る問題は基本的に地域的な慣習に基づく話し合いによって解決が図られるのだという。しかしお互いの利害が真っ向から対立する場合には、平和的に解決するのは至難の業であるらしい。
「ツナミという言葉は知ってる?」
と僕はサディアに訊いてみた。彼女の関心事が雨であることはわかったが、外の世界の情報も少しぐらいは入ってくるだろうと思ったのである。「ツナミ」という言葉は、3ヶ月前にインドネシア沖で起こった大津波によって、世界中に知られるようになっていた。
ところが、彼女はあっさりと首を振った。
「ツナミ? そんな言葉知らないわ」
どうやら、この村に立ち寄った外部の人間は、誰もツナミについて話さなかったようだった。
「地震によって、とてつもなく大きな波が起こったんだよ。30万もの人が波に飲み込まれて死んだんだ」
僕はそう説明したが、サディアはよくわからないという風に首をかしげるばかりだった。それも無理からぬことではあった。生まれてから一度も海を見たことがない彼女が、高さ15メートルもの波が突然襲いかかってくるというイメージを想像できるはずはないのだから。
サディアにとって雨と同様に関心があるのは、結婚相手の男性選びだった。二十歳といえば、このあたりではまさに結婚適齢期なのである。
「どんなタイプの男性がいいの?」と僕が訊くと、
「あなたがいいわ」とサディアは答えた。
もちろん冗談なのだが、僕らが出発しようかと腰を上げたときにも、「あなたはここにいなさいよ」と言ってきたぐらいだから、何パーセントかは本心だったのかもしれない。
異国の女の子に気に入られて、居残り指名を受けるなんて滅多にないことだったので、素直に嬉しかった。だけど、もしこんな辺境で一泊しようものなら、翌日には結婚の儀式まで済まされてしまいそうで怖かった。
結婚したら最後、津波のニュースさえ届かないようなところで、毎日雨を待ちながら暮らすことになるのだ。そんな生活には耐えられそうになかった。
「いいからマサシはここに残れよ。僕たちは先に行くからさ」
ウィリアムはそう言って笑った。まったく、他人事だと思って勝手なことを言いやがる。
「いつかまた来るよ」
僕はサディアにそう言い残して、足早に玄関を飛び出した。
|
|
|
|