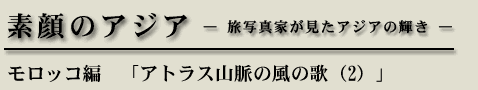|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
薪を背負った女たちの歌声とすれ違った日の夜、僕らはアメスカという村に泊まった。アメスカ村はアトラス山脈に点在するベルベル人集落の中でも、かなりの辺境に位置している。村人は山に囲まれたわずかな耕作地に麦や野菜を植えて、細々と生活の糧を得ている。住民の家屋は急な傾斜を持つ崖にしがみつくようにして建っている。人々は夕方になると家の外に出て、世間話をしながら日向ぼっこをする。そして見慣れない外国人が通りかかると、少しはにかんだ笑顔を向けてくれるのだった。
アメスカ村にある唯一の宿屋は、典型的なモロッコの田舎の民宿だった。特徴的なのは部屋が異様に細長いことである。縦が畳1畳半ぐらいの長さなのに、横は畳8畳分ぐらいあるのだ。その細長い部屋の床には、色とりどりの絨毯が敷き詰められ、その上に分厚い毛布が何枚も積み上げられていた。それは冬の冷え込みの厳しさを物語っていた。
質素な夕食を済ませてしまうと、もうやるべき事は何もないので、僕らは早々に毛布にくるまって横になった。電気もなくテレビもないアメスカ村の夜が更けるのはとても早く、旅行者もそれに合わせて自然と早寝早起きになってしまうのである。
|
 |
|
夜中、何かの声で目を覚ました。最初は動物の鳴き声だと思った。フクロウみたいな鳥か、あるいはオオカミの遠吠えか。しかし動物の声にしては整いすぎているようにも思った。
部屋の中は真っ暗だった。目を開けているのか閉じているのかわからないほどの濃密な闇が僕を包んでいた。午前4時か5時ぐらいだろうと見当をつけたが、それを確かめる術はなかった。僕は二枚重ねた分厚い毛布を口元に引き寄せて、その不思議な音に耳を澄ませた。
しばらくの間、「それ」は試すようにいろいろな音を出していたのだが、次第にメロディーらしきものを奏で始めた。ということはやはり動物の声ではなく、楽器なのだろう。角笛か管楽器の音だろうか。清らかなのだが、どことなく物悲しさを湛えた音色だった。
毎朝5時にイスラムの礼拝を呼びかける声・アザーンが響くはずだとガイドは言っていたが、この音がそうだとは思えなかった。礼拝の呼びかけにしては、あまりにも自己完結的過ぎるのである。誰かに何かを呼びかけているというよりは、自分の心の内にある声をメロディーに託しているように聞こえるのだ。
村はしんと静まり返っていた。人の話し声も家畜の鳴き声もない。その静寂の中を、奇妙な旋律だけがゆらゆらと漂っていた。耳を澄ませていると、分厚い壁の向こうに「それ」を吹いている人の息づかいや孤独を感じることができる気がした。僕は今「風の歌」を聴いているのかもしれない。そんな風に思った。
どのぐらいの時間、耳を澄ませていただろうか。5分ぐらいだった気もするし、30分以上経っていたようにも思う。始まったのも唐突なら、終わったのも唐突だった。その演奏(あるいは独白)が止むと、もう何も聞こえなかった。村を囲む山々が音という音を全て吸収しているようだった。
朝起きてからガイドにその話をすると、「そんな不思議な音の話は聞いたことがないですね。夢でも見ていたんじゃないですか?」と笑われた。結局、その音の正体はわからないままだった。あるいはガイドの言うように僕は幻の歌を聴いていただけなのかもしれない。
モロッコで聞いたいくつかの音は、独特の美しさを持っていた。それは決して何かの媒体に記録できるものではなかった。
もちろんこの音をレコーダーに録音し、再生することはできる。しかしそれらの音は単なる空気の振動ではない。荒々しい山肌や、直線的な太陽の光や、人を寄せ付けない土地に訪れる春の気配といったもの全てを含んでいるのである。
たぶん、僕らは全てを記録することができないからこそ、旅をするのだ。太陽の温かさを感じ、渓流の冷たさを知り、静寂の中に響く小さな音に耳を澄ませること。それが僕らが異国を歩く理由なのだ。
|
|
|
|