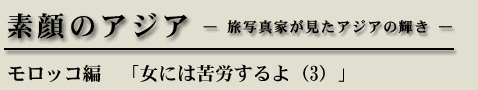|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| バンコクのカオサン通りにはユニークな旅人が多い。彼女はタンザニア出身で画家の卵なのだそうだ。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
1ヶ月のモロッコ取材旅行を終えた僕らは、直接日本には帰らずに、タイのバンコクに立ち寄った。ここで二、三日のんびりしながら、世界中のバックパッカーへのインタビューをとることにしたからである。
バンコクのカオサン通り周辺は、ウィリアムが求めるクールな旅人――奇抜なファッションやファンキーな髪型やユニークな経歴を持つ若者――が大勢集まってくる場所なので、取材は実にスムーズに進んだ。
夜は暇だったので、カオサン通りの喧噪の中をぶらぶらと歩いた。夜のカオサン通りにはいつものようにオカマたちがたくさんいた。たぶんオカマバーの客引きなのだろう。露出度の高いドレスを着て、甲高い声で旅行者に話し掛けていた。
当然のことながら、オカマにも「美しいオカマ」と「美しくないオカマ」が存在しているのだが、美しさの度合いが下がるほど(つまり醜くなればなるほど)、衣装の露出度が上がっていく傾向があった。
容姿の美醜と露出度との相関関係は、本当に見事なものだった。例えば、お笑いコンビのアンガールズのように背が高くガリガリに痩せていてカマキリのような顔をしたオカマは、普通に立っているだけでもパンツが見えてしまうほど丈の短いスカートを履いていた。彼女は彼女なりに必死だということはわかるのだが、何もそこまでしなくてもいいじゃないかと思った。
ところで、ウィリアムは「レディボーイ(オカマ)のスペシャリスト」を自認する男である。彼は数年前バンコクに住んでいたことがあるのだが、そのときにオカマバーに通ったお陰で、すっかりその筋の事情に詳しくなったのだという。
彼がオカマについての持論を熱く語ってくれたのは、僕が日本に帰る前夜のことだった。その日、彼は一人でオカマバーに出かけ、午前2時を回る頃になってようやく部屋に戻ってきた。
「アメージングな夜だったよ」
とウィリアムは興奮気味に話し始めた。
「今日、僕が飲みに行ったバーはホステスの半分がレディーボーイで、残りの半分が正真正銘の女の子というちょっと変わった店だったんだ。でもレディーボーイか本物の女かはすぐに見分けがつくから問題はない。僕はスペシャリストだからね。本物か偽物かは99.9%見分けられるんだ」
彼はそこまで一気に話すと、ペットボトルの水を口に含み、エアコンのスイッチを入れた。古びたエアコンがブーンというまどろっこしそうな音を立てて動き出した。バンコクの夜はいつものように蒸し暑かった。
「ところが、今日僕のそばにやってきた女の子は、レディーボーイなのか本物の女なのかが最後までわからなかったんだ。彼女は本当に美しかった。普通の女として見ても、相当にレベルが高いと思うよ。レディーボーイを見分けるには、いくつかのポイントがあるんだ。のど仏、声の調子、肩幅、お尻の肉付きなんかだ。僕はそのポイントをひとつひとつチェックしていった。ひとつも不自然なところはなかった。女に違いない。そう僕は結論づけた。でも、どこかひっかかる部分があったんだ。具体的にどこがどうとは言えないんだけど、何となく変な気がしたんだ。それで、彼女が席を立った隙に、別の従業員に尋ねてみたんだ。『あの子は本物の女なのか?』って。すると彼女はこう答えた。『もちろんよ。女の子に決まってるわ』。それから彼女はイタズラっぽく笑って、人差し指と中指をチョキチョキとさせた。ハサミみたいにさ」
「どういうこと?」
「つまりさ、ハサミでちょん切ったってことだよ。ペニスをね。ファック! 彼女は『今』は女だけれど、『昔』は男だったってことさ。手術をしたってわけだ」
ウィリアムはそのとき自分がいかに驚いたのか、そのオカマがいかに美しかったのかを熱っぽく語った。オカマの専門家をまんまと騙すぐらいだから、僕がその場にいたら女だと信じて疑わなかっただろう。
「彼女がレディーボーイだってことがわかって、残念だった?」と僕は訊ねた。
「いいや、残念じゃなかった。僕の目的はセックスじゃないからね。実を言うと、その子にもベッドに誘われたんだ。でも、男だろうが女だろうが、僕は金を払ってセックスしようとは思わない。今は妻や子供もいる立場だからね」
「じゃあ、何のためにバーに行ったんだい?」
「さっきも言ったように、99.9%のレディーボーイは見分けがつく。もともと男なんだから当たり前さ。いくら手術をしたって、誤魔化しきれないところがどうしても出てくる。ところが今夜のようにどうしても見分けられない人も0.1%はいる。それは奇跡なんだ。僕の目は『彼女は本物の女だ』と認識しているのに、頭には『彼女はレディーボーイだ』という情報がインプットされている。感覚が裏切られているわけだ。寿司屋で寿司を頼んで、口に入れてみるとハンバーガーの味がするようなものさ。そいつを奇跡と呼ばずして、何と呼べばいい?」
「マジックショーを見に行っているみたいなもの?」
「その通り! イッツ・マジック! だってね、女性はもともと女性に生まれているわけだから、綺麗でも驚くことはない。ところがレディーボーイは、男の体に生まれながら女性の美しさを手に入れているわけだ。お金もかかっているし、努力だって必要だ。まったくもって、アメージングな存在なんだよ」
僕はあいにくオカマのいるお店に通ったこともないし、見分けがつかないようなハイレベルなオカマに出会ったこともない。それでも、ウィリアムの語る「オカマの魅力」には、妙な説得力があった。
女性の美しさというものは自然に備わったものであり、それを過剰に磨こうとするのは、かえって醜いことではないかと僕は思っている。肌の白さにこだわるあまり、本来の自分の顔を見失ってしまった鈴木その子などが、そのいい例だろう。
しかしオカマというのは、「美しさへの飢餓感」というものを宿命的に持っていて、それを日々追求している存在である。男に生まれてしまった以上、彼女たちに「ナチュラルビューティー」はあり得ないのだ。
そう考えれば、ウィリアムがオカマにアメージングさを感じるのもよく理解できる。美しいオカマに出会うことは、精緻に作り込まれた人形の美しさに感動するようなものなのかもしれない。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
バンコクのカオサン通りにはユニークなカップルも多い。
この二人は40歳(!)の日本人男性と、20歳のイギリス人女性という異色のカップルだった。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
|