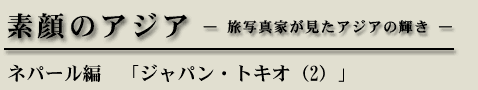|
 |
|
|
|
 |
|
 |
夜になると、ゴータレ村の村人たちが僕が泊まっている農家の庭に集まってきた。「アメリカ人ってのはどんな奴なんだろうな?」と言っているのかどうかは知らないが、珍しいものが来たから一度見ておこうという感じで、村人のほぼ全員が集結したのである。
僕の傍らには、僕の顔を照らすための専用ランプが置かれ、村人はそれを取り囲むように座った。僕には村人の顔は見えないが、村人からは僕の顔がよく見える。まるで一人芝居をする舞台俳優にでもなった気分だった。
僕は一緒に旅をしているネパール人のガイドを通じて、村人たちにいくつかの質問を投げかけてみた。しかし返事が返ってくるまでに、ひどく時間がかかった。例えば「日本について何か知っていますか?」という比較的答えるのが容易だと思われる質問にも、答えを得るまでに10分以上かかった。まずガイドのアルンが質問のあらましを説明する。それについて村の長老たちが何かを訊ねる。アルンがそれに答える。今度は村人同士がガヤガヤと話し合う。再び長老がアルンに質問をする。アルンが答える。そんなやりとりが延々と繰り返されるのである。
「ヒロシマとナガサキなら知っている」
やっと返ってきたのは、こんな答えだった。歴史上初めて原爆を落とされた土地の名前は、ネパールの山村にも響いていたのだ。
「ジャパン・トキオなら俺も知ってるぜ」
若い男が口をはさむと、一同からどっと笑い声が起こった。さすがに首都である東京の名前は知れ渡っているのか。そう思ったのだが、実は「ジャパン・トキオ」には別の意味があるらしい。
「ジャパン・トキオというのは、ネパールで大ヒットした歌のタイトルなんです」とアルンが説明してくれた。「3年ぐらい前からかな、ラジオで毎日流れるようになったんです。今では知らない人はいませんよ」
それじゃぜひ歌ってみてよ、と村の若者に頼むと、十人ほどの女の子が声を合わせて歌い出した。彼女たちの歌う「ジャパン・トキオ」のメロディーは明るく軽快なものだったので、豊かな国・日本への憧れを歌っているのかとも思ったのだが、実はそうではなかった。ネパール語の歌詞は次のようなものだった。
「ジャーパン・トキオ・モイレチティ・ポターコイ・ティエーニ・コタロキオー」
日本語に訳すと、「私は日本の東京に手紙を送った。しかしあの人には届かなかった」という意味になるという。
ネパールの山村に住む若い男女が結婚した。しかし結婚式の直後から、夫は日本へ出稼ぎに行くことになり、離ればなれになってしまう。妻は夫の帰りを待ちわびながら、その気持ちを手紙に綴って東京に送る。しかしどういうわけか、その手紙は夫の元には届かない。日本での過酷な労働に耐えている夫も、妻への想いを手紙に綴るのだが、その手紙もまたネパールには届かない。二人のすれ違いは続く。そういう切ない歌だった。
ネパール人男性の多くが外国へ出稼ぎに行く。日本だけではなく、インドやアラブの産油国などにも多くの労働力が「輸出」されている。ネパール国内には十分な仕事がないのである。この歌にはこのようなネパールの出稼ぎ労働者たちの悲哀が込められていて、それが山村に住む人々の心を打ったのだろう。
「ジャパン・トキオ」に歌われているように、結婚直後に夫が出稼ぎに行って、離ればなれになる夫婦は珍しくないが、結婚式の直前に出稼ぎに行くことが決まって、新郎不在のまま結婚式を挙げてしまう夫婦までいた。僕がたまたま立ち会うことになったのは、式の三日前に新郎がカタールに行ってしまい、この先2年間は会うこともできないという夫婦の(夫不在の)結婚式だった。
「結婚式よりも、外国の就労ビザが取れることの方がずっと大事なんです」と新郎の弟が僕に言った。ビザがいつ下りるかは直前までわからないから、その知らせが入るとすぐ荷物をまとめて旅立つのだという。それならば結婚式の方を延期すればいいのではないかと思うのだが、弟は「何十人もの親戚を招待しているんです。今更中止にするわけにはいきません」と言うのだった。ネパールにおける結婚式は、夫婦のためというより、お互いの家族同士、親戚同士のために行うものなのかもしれない。
|
|
|
もっとも、このような「遠距離結婚」が常にうまく行くわけではない。ゴータレ村でも夫が出稼ぎに行っている間に、妻が他の男と不倫関係になり、三人の子供を残して駆け落ちしたという事件が起こったのだそうだ。この出来事は伝統と秩序を重んじる村人にとって、大変ショックな出来事だったらしい。
村の長老によれば、このような「ふしだら」な行為が行われるようになった背景には、若い世代が伝統文化を軽んじるようになったことがあるという。ネパール人は共通語としてのネパール語を学校で習い、ほとんどの人がそれを話せるのだが、村人同士の会話はネパール語とは別の民族語であるマガル語で行っている。しかしマガル語には文字がないので、村の歴史や伝統は全て口承で伝えられているのである。つまりマガル語を話す人間がいなくなれば、村の歴史や伝統は消えてしまう。そうなると、村の秩序も失われてしまう。長老はそれを恐れているのだ。
ガイドによれば、ゴータレ村は隣村と離れているうえに、村人全員が同じカーストに属しているので、保守的な気質を持つことで知られているという。よそ者に対しては礼儀を持って迎えるが、決して信用はしない。村の外は異世界であり、外から入ってくる情報や文化はできるだけ退けたい。そのような考え方は、長老の言葉からも伝わってきた。
そんなわけで、ゴータレ村の人々と僕の間には、ある種の緊張感を伴った距離があった。人々は初めて目にする外国人をどう扱っていいかわからず、戸惑っていた。その緊張を解くきっかけとなったのが、「ジャパン・トキオ」だったのだ。
ネパールの民謡は、男グループと女グループが交互に行う「紅白歌合戦」形式を取るのが普通であり、「ジャパン・トキオ」においても、男の子たちが出稼ぎに行った夫の気持ちを歌い、その後に女の子たちが村に残った妻の気持ちを歌った。
歌合戦が一通り終わると、今度は踊りが始まった。体をくるくるとターンさせながら、腕と手に表情をつけて即興で踊るのが、山村の伝統的な踊り方だった。僕も女の子たちに引っ張られるようにして踊りの輪の中に加えられ、見よう見まねで踊ったのだが、最初はリズムを掴むのに苦労して、なかなか上手く踊れなかった。
そんな僕の様子を見て、村人たちはおかしそうに笑った。陽気なおばさんが「ダメだねぇ、こうやって踊るんだよ」と手を取ってレクチャーしてくれる。何だ、外国人といっても我々とそんなに変わらないじゃないか。村人たちは徐々にそう思い始めてくれているようだった。
言葉がわからなくても歌をうたうことはできるし、踊りをおどることはできる。同じ場所に立って、同じ空気を吸うこと。同じ体験を共有することによって、僕らの間の壁は少しずつ取り払われていった。
|
|
 |
|
 |
|
|