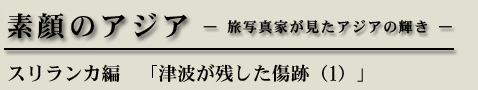|
 |
|
|
|
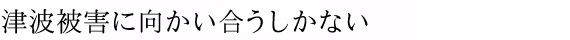 |
|
 |
|
|
 |
スリランカ南部のツナミエリアを訪れた後、しばらくスリランカ中部の町を旅した。ローカルバスを乗り継いで、山岳地帯の町バンダーラウェラや、古都のキャンディ、遺跡の町アヌーラダプラなどを転々とした。
しかし、僕にとってこれらの町はひたすら退屈だった。仏教遺跡は壮麗なものだったし、切り立った山の連なる景観や、流れ落ちる滝もそれなりに見応えがあった。しかしそれは「すぐに薄らいでしまうだろう」という予感を伴った感動だった。
おそらく僕の中に刻み込まれた津波の傷跡の記憶が、普通に旅を楽しむという事を難しくさせていたのだと思う。こうなった以上は、やはり津波被害に正面から向かい合って旅を続けるしかないだろう。僕はそう腹をくくって、再びツナミエリアに向かったのだった。
僕がまず訪れたのは、スリランカ東岸に面した港町トリンコマリーだった。トリンコマリーの市街地は外海に対して閉じた入り江の奥にあるので、津波の被害はほとんど見られなかった。港には何十隻もの漁船がとも綱に繋がれて、静かな波に揺られていた。壊れた漁船も見当たらず、港は平和そのものだった。
しかし港の反対側にある砂浜に面した漁村は、あちこちで家が倒壊するなどの大きな被害を受けていた。砂浜には津波の影響によって打ち上げられた漂流物が散乱していた。ゴミや海草類だけではなく、重そうな流木も数多く横たわっている。船を失った漁師達はこの流木を斧で細かく切断し、煮炊きの燃料として町に運んでいた。今のところそれぐらいしか仕事がないのである。
「昨日は流木と一緒に、死体が流れ着いたんだ」と漁師の一人が流れる汗を拭いながら言った。「どうもインドネシア人のものらしいね。一ヶ月以上前のものだから、ほとんど白骨化していたいようだが」
何千キロも離れた場所に大木を送り、さらに死体まで送りつける。僕は今更ながら津波の威力の凄まじさを思い知らされた。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| インドネシアから流れ着いたという流木を切り出している青年。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
トリンコマリーの郊外をぶらぶらと歩いていると、古い足踏み式ミシンを使ってスーツを仕立てている男に呼び止められた。彼の仕立て屋も津波の被害を受け、四台あったミシンのうち使い物になるのは一台だけになってしまったという。電気式のいいやつはみんな壊れたが、もっとも古株の足踏み式だけは壊れなかった。
「でも仕事が続けられているだけ好運だよ」と彼は苦笑いを浮かべて言った。
彼の左腕の手首のあたりに丸い火傷の痕が三つ並んでいたので、それはどうしたんだと聞いてみた。傷はまだ生々しかったから、津波で負ったものなのかと思ったのだ。
彼は陽気な男だったが、僕が傷跡について質問したときだけは表情を曇らせた。言葉に詰まり、どう話したらいいのか、しばらく考えていた。
「俺の恋人がツナミで死んでしまったんだ」
と彼は表通りに目を向けて言った。その目は少し充血しているように見えた。
「悲しくて、痛くて、涙が止まらなかった。だから火のついたタバコをここに押しつけたんだ」
「火のついたタバコを?」
僕は驚いて聞き返した。
「ああ。馬鹿馬鹿しい事だってあんたは思うかもしれない。でもそうしないわけにはいかなかったんだ」
彼はそう言うと、その痛みを確かめるように右手で傷跡に触れた。「根性焼き」という言葉が日本にもあるが、彼はそれと同じ行為をしたというのである。しかも火傷の痕が三つ並んでいるという事は、彼が一度ならず二度三度と火傷の痛みに耐えた事を意味していた。
彼は恋人を失った心の痛みを肉体の傷として体に刻み込みたかったのだろう。その痛みの記憶を忘れないための印を求めたのだ。あるいは彼は自分だけが助かって、彼女が死んでしまった事が、どうしても許せなくて、自分自身に罰を与えようとしたのかもしれない。
しかし彼の本当の痛みの鋭さや、傷の深さは僕には到底知り得ない事だった。だから僕は彼に何の言葉もかけることができなかった。三つ並んだ薄桃色の火傷の痕を、ただ黙って見つめるばかりだった。
|
|
|
|