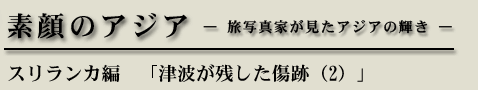|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
トリンコマリーに着いた翌日、自転車でニラヴェリという漁村に行ってみることにした。この辺りではニラヴェリがもっとも大きな津波被害を受けたのだと、宿の主人に聞いたからだ。ニラヴェリはトリンコマリーから北へ十五キロほど行ったところにある。真昼の射るような強烈な日差しの中、十五キロも自転車を漕ぎ続けるのは体力的にきついだろうが、朝早く出発すれば大丈夫だろうと踏んだのである。
トリンコマリーの町並みを抜けると、道路を行き交う車の量は急激に少なくなった。荷台に人をたくさん乗せたトラクターや、自転車の二人乗りをしている人々と時々すれ違うだけである。面白いことに、スリランカの二人乗りは同乗者が漕ぎ手の前に座る。映画「ニュー・シネマ・パラダイス」で映写技師のおっさんが主人公の子供を乗せていたようなスタイルである。この「シネパラ乗り」はスリランカ中どこででも目にする。学校へ行く子供を父親が送っていくときも、恋人同士で映画館に出かけるときも、若者二人が同じ職場を目指すときも、とにかくみんな「シネパラ乗り」なのである。僕はこの乗り方を試したことがないのではっきりしたことは言えないのだが、姿勢としてはかなり窮屈そうである。運転する方もバランスを取るのが難しいだろうと思う。それにもかかわらずスリランカ人がこの乗り方にこだわるのは何故なのか。ずっとその理由が知りたかったのだが、残念ながら納得できる答えは見つけられなかった。
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
ニラヴェリは徹底的な破壊を受けていた。砂浜に沿った家々の大半が倒壊し、瓦礫の山と化していた。ほとんどの住人達は難民キャンプで暮らしているらしく、人の気配が全くなかった。ときどき動くものの気配を感じて振り返っても、そこには野良犬かカラスの姿しかなかった。太古の昔ここに人が住む村があった――そのような立て札の立つ遺跡の中を歩いているような気がした。
ニラヴェリはスリランカ東岸でも有数の美しいビーチを持ち、将来はリゾート地としての開発も期待されていたところだったのだが、今は見る影もなかった。海岸はゴミと流木で埋まり、砂浜はいたるところで深くえぐられていた。
あらゆるものが破壊された土地で、独特の存在感を示していたのは椰子の木だった。砂浜に立つ椰子の木は、根っこを地表に露出させながらも、倒れることなくすっくと立っていた。彼らは地中深くまで根を下ろし、しっかりと大地を掴んで津波の圧力に耐えたのだ。その姿は植物の持つ本質的な強さを誇示しているようだった。
動物は事前に災害を察知していち早く逃げた。植物は地中深く根を張って波に耐えた。人間だけが第六感を持たず、根も張ることもせず、無防備に自然と向き合っていたのだ。そんなことを思いながら、僕は無人の砂浜を自転車を押して歩いた。
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
| ニラヴェリの難民キャンプから井戸に水を汲みに行く姉弟。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
海岸沿いを北に一キロほど行ったところに、ようやく人々が集まって作業をしている場所を見つけた。若い男達が土を練って日干し煉瓦を作り、それを積み上げて大きな建物を建てている。海岸に近いところでは、壊れたプールを作り直しているようだった。
「ここには元々大きなリゾートホテルが建っていたんだよ」
僕が男達の作業を眺めていると、一人の男が流暢な英語で説明してくれた。セルバラージと名乗った男は、漁師として舟を出す傍ら、この村で唯一のツーリストガイドをしていたのだそうだ。しかし今は他の漁師と同じように仕事を失って、ホテルの再建を手伝っている。
「ここのオーナーは金持ちでね。だからツナミのあと、すぐに再建を始められたんだ。たぶん来月には営業を再開できるんじゃないかな」
彼の言葉を信じるなら、かなりの突貫工事であるが(修復といっても津波の後も残っているのは土台くらいなのだ)、作業の様子を見ていると、それにも納得することができた。一応鉄筋コンクリートの支柱は何本かあるのだが、それ以外はただ日干し煉瓦を積み上げただけの非常に簡素な造りなのだ。これでは大津波や地震が再び起こったらひとたまりもないだろう。災害の教訓を生かして頑強な建物を建てるだけの余裕はここにはないのだ。
セルバラージさんは廃墟と化した村の中を歩きながら、津波被害の様子を説明してくれた。「この家は奥さんと息子が死んだ。ここは一家六人が死んだ。ここは主人と赤ん坊が死んだ」といった具合に、どこで誰が死んだかということを事細かく教えてくれたのだ。彼によれば、津波は三度に渡って海岸を襲い、波の高さは回を重ねる事に高くなっていったという。
「三度目なんて波とは言えないね。海そのものがごっそり一キロ移動してきた、という言い方が正しいんじゃないかな」と彼は肩をすくめて言った。
それから、僕はセルバラージさんと一緒に、彼の家族が暮らしている難民キャンプに向かった。難民キャンプは村から三十分ほど歩いた空き地にあった。くすんだ緑色のテントが四十個ほど集まっていた。
「実は我々にとって難民キャンプ暮らしは初めてのことじゃないんだよ」と彼は言った。「二十年前に内戦が始まったときも、こんな風に自分の家を追われて暮らしていたんだ。でもあのときはテントじゃなかったから、今よりはいくらかマシだったな。なにしろこのテントは暑すぎるんだ。昼間はとても中に居られない。しかもこれからスリランカはもっと暑くなる。このままだと体がおかしくなってしまうよ」
テント暮らしも一ヶ月を超えていたので、避難民の顔にも濃い疲労の色が滲み出ていた。子供達は元気に走り回っていたが、大人はだいたい家の外でぐったりと寝そべって、午後の暑さをやり過ごしていた。
|
|