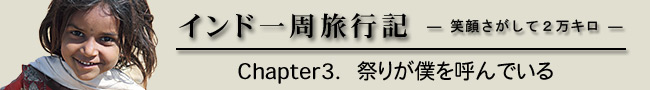|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
ババババン!
突然、何かが爆発したような大きな音で、僕は目を覚ました。とっさに枕元に置いてあるペンライトをつけて、部屋の中を照らしてみた。
異常はない。シミだらけの壁、天井から吊り下がるファン、旧式のテレビ。どこにでもあるインドの安宿の一室だ。
爆音は表の大通りから聞こえてきた。まだぼんやりとしている頭に「テロ」の二文字が浮かんだが、すぐに「そんなわけない」と頭を振った。ここはアンドラ・プラデシュ州の平和な田舎町。山岳ゲリラに怯えるコンタと違って、そんな物騒なことが起こるはずはない。町の名前は確かマフブババードといったっけ。何度も町の人に聞き直して、ようやく覚えたのだ。
爆竹だな、これは。
まともに頭が働くようになれば、簡単にわかることだった。爆竹特有の乾いた連続音。何かを祝うために鳴らされているのだろう。それにしても凄まじい量だ。旧正月を祝う中華街にも匹敵するかもしれない。
詳しいことはわからないが、なにやら面白いことが始まりそうだ。僕はカメラをひっつかんで部屋を飛び出した。
表通りには爆竹の煙と火薬の臭いが充満していた。既に大量の爆竹を使ったはずなのだが、点火役の男の手には未使用の爆竹の束がまだいくつも握られていた。爆竹と共にロケット花火も景気よく打ち上げられている。今日は祭りなんだから眠っちゃいけないよ。そんなことを町中の人々に知らせているみたいだった。
もうもうと立ちこめる煙の中から姿を現したのは、黒い布だけを腰に巻いた半裸の男たちだった。両手に灯明を携えた男が先頭に立ち、大声で歌をうたいながら歩いている。歌に合わせて狂ったように踊る一団があとに続く。夜もすっかり更けているというのに、男たちのテンションは異様に高い。
「我々が黒を着るのは、ヒンドゥー教の神様の一人であるアイヤッパが黒を好むからだ」
と教えてくれたのは、まるでプロレスラーのような体格の大男だった。身長は190cm近くあり、とんでもなく分厚い胸板を持っている。すでに全身汗びっしょりである。
「我々はこれからアイヤッパに祈りを捧げに行く。アイヤッパはビシュヌ神とシヴァ神のあいだに生まれた神様だ。とても力があり、とても美しく、そして・・・・」
大男はその大きな顔を思いきり近づけて、口から唾を飛ばしながら、敬愛するアイヤッパ神について熱心に話し始めた。しかし彼が話す英語はインド訛りが強いうえにとても早口だったので、半分も理解できなかった。
「・・・というのがアイヤッパなんだ。わかったかい?」
「・・・なるほど」
僕は頷いた。何らかの感想が求められているような雰囲気だったので、
「アイヤッパというのはパワフルな神様なんですね」
と適当にまとめてみると、大男は「その通りだ」と満足そうに頷いた。
行列はマフブババードの町を1時間近く練り歩いた後、寺院の隣にある広場に入った。ここでメインイベントの儀式が行われるという。
広場には既に何百人もの見物客がひしめき合っていて、とても儀式を間近で見られそうにはなかったのだが、例の大男が警備係に口添えしてくれたおかげで、なんとかいい場所に潜り込むことができた。感謝。顔はおっかないが、なかなか親切な男なのだ。
僕が陣取った場所にはすでにカメラを持ったインド人が何人も待機していた。祭りの関係者やプロのカメラマンたちだ。その中の一人が僕のカメラについてあれこれ訊ねてきた。スペックや値段など、かなり突っ込んだ質問だった。
「やっぱり日本のカメラは最高だな。私も欲しいんだけど、こういうものはインドでは高いからね」
カメラマン氏は羨ましそうに言った。彼によれば、近年インドでもフィルムカメラからデジタルカメラへのシフトが急速に進んでいるという。フィルム代と現像代がかからないのが何よりの利点なのだ。
「ところで、この祭りの情報はどこで手に入れたんだい?」
「偶然ですよ」と僕は言った。「宿で寝ていたら爆竹の音がした。外に出てみると行列がやってきた。彼らについて歩いていると、ここに来てしまったんです。祭りが僕を呼んだんですよ」
「祭りが君を呼ぶ。そりゃ、いいね」
彼は楽しそうに笑った。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| バドラチャラムという町で出会った祭り。お神輿が町中を練り歩く |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
インドを旅するあいだ、僕はいくつもの祭りに遭遇したが、いずれも「どこそこで祭りをやっている」という情報を事前に仕入れていたわけではなく、偶然に出会ったものばかりだった。バイクを走らせていると、どこかから賑やかな音楽が聞こえてきたり、青空に打ち上げ花火が上がったり、目の前におみこしを担いだ行列が現れたりするのだ。
もともと僕はそれほど祭り好きの人間ではない。夏の花火大会や、神社のお祭りなど、たくさんの人でごった返す場所を好まないということもあるし、大勢の人と一緒になって盛り上がるということが性格的に苦手だということもある。松本人志が自著の中で「同級生の担ぐおみこしの行列を電柱の影から覗いているような子供だった」と書いていたが、その気持ちはよくわかる。
僕の写真も「ハレ」よりも「ケ」のシーンを撮ったものの方が圧倒的に多い。日常の何気ない場面に宿る輝きに惹かれるのだ。
しかしインドでは祭りが僕を呼ぶのである。面白いものを見せてやるからこっちへ来い、と誘うのである。強い力で。それはインドの日常には祭りが不可欠だということを意味しているのだと思う。この土地では祭りは特別なものであると同時に、特別なものではないのだ。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 日常の憂さを晴らすかのように歌い踊るのがインドの祭りだ |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|