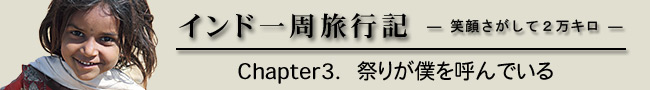|
|
|
 |
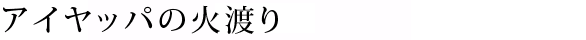 |
 |
 |
広場の中心では、儀式の準備が進んでいた。まず一本の大木が運ばれてきて、それに火が放たれる。木はしばらくのあいだ勢いよく燃えさかり、暗闇の中に無数の火の粉を舞い散らせる。それから数人の男たちが火かき棒を振るって木を砕き、無数の炭の断片を作る。その炭を3メートル四方ほどの浅い穴に敷き詰めていく。それから大きなうちわを持った男がやってきて、敷き詰めた炭に風を送り込む。新鮮な空気を送られた炭はさらに温度を上げて、オレンジ色に輝き始める。凄まじい熱風が僕らの方にも吹きつけてくる。早い話、巨大な「焼き鳥用の炭火コンロ」が完成したわけである。
この炭火コンロの上を裸足で歩くのが、この儀式のハイライトである。これは理屈抜きで凄かった。真っ赤に燃える炭火の表面が何百度なのかは知らないが、とんでもない高温であることは間違いない。そこをわざわざ裸足で渡るのである。なるべく涼しい顔をして。
「あなたは毎年火の上を走っているんですか?」
僕は親切な大男に訊ねてみた。炭火を渡り終えたばかりの彼は、すぐに二巡目の行列に並ぼうとしていた。信徒たちは炭火が消えるまで何度も何度も火渡りを繰り返すのである。
「走るんじゃない。歩くんだ」
彼はやや憮然とした口調で訂正した。
「もちろん、この儀式には毎年参加している」
「足の裏は何ともない?」
「ノープロブレム。熱いとも感じないさ。なぜならアイヤッパが我々を守ってくださるからだ。神様は全てを見ているんだ!」
彼は分厚い胸をさらに反らせて言った。しかしそうは言っても、炭火の表面が高温なのは動かしがたい事実である。神様がいてもいなくても、然るべき時間が経てば炭火の上の焼き鳥はこんがりと焼ける。その物理現象に対する肉体的な反応を、信仰心と精神力でもってどのように押さえ込むか。それがこの儀式のポイントだった。彼らは忍耐と集中力の限界を試しているのだ。
日本にも「心頭滅却すれば火もまた涼し」という言葉がある。しかし、実際にその境地にまで達した人はインドにもなかなかいないようだった。「走るんじゃない。歩くんだ」と大男は言ったが、僕の見たところ「歩いている」と認定できる人は少数であり、大多数の信徒は炭の上を小走りで駆け抜けていたのだ。神様が守ってくれたって、やはり熱いものは熱いのである。
しかし、集まっている観衆の反応はシビアだった。ぴょんぴょんぴょんと三段跳びの要領で炭を飛び越えていくようなヤワな信徒には、失笑と容赦のないブーイングが浴びせられ、まるで子犬を連れて公園を散歩しているかのように涼しい顔でゆっくりと歩く男には、惜しみない賞賛の声が送られるのだった。
|
|
|
火渡りを行った信徒は全部で百人ほどだったが、その中には子供も含まれていた。10歳ぐらいの女の子も二人いた。彼女たちも大人と同じように真っ黒い服を着て炭火の前に立ったのだが、その後の行動は対照的だった。ショートカットの女の子は「ヤー!」という叫び声を上げながら一気に走り抜けたのだが、もう一人の髪の長い子はあまりの熱気に足がすくんでしまい、ついに泣き出してしまったのだ。
この熱風だもの。ビビるのが当たり前だよ。僕は心から彼女に同情した。
|
|
|
午後11時半に始まった火渡りの儀式は興奮のうちにピークを迎え、その熱気の渦は見守る観衆にも飛び火していった。儀式を行う信徒たちと一般の観衆のあいだは木の柵で仕切られているのだが、興奮を抑えきれなくなった人々が我先にと柵を乗り越えて中に入り始めたのだ。まるでベルリンの壁の崩壊を喜ぶ東ベルリン市民のような勢いで。
会場は大混乱に陥るかに見えたが、祭りの運営側もこうした事態を予測していたらく、すぐさま対策が講じられた。柵を乗り越えた人々は、十人以上いる警察官によってことごとく追い払われたのである。警官は乱暴だった。手に持った長い棒で人々の背中を思いきり叩くのだ。相手が女だろうが子供だろうが容赦しない。ひっつかんでは叩き、ひっつかんでは叩く。そうすると人の波はさーっと引いていくのだが、しばらくするとまた懲りない人々が柵を乗り越えようとする。それを見つけた警察官がボコボコに叩く。また波が引く。まるでモグラ叩きをしているかのような観衆と警官の攻防戦は、儀式が終わるまで延々と繰り返されたのだった。
それはあまりにもインド的な光景だった。人を殴ることを何とも思わない威張りくさった警察官と、決められたルールを遵守する気のない自分勝手な人々。どちらも大真面目なだけに、そこに含まれる滑稽さも際立っていた。
宗教的情熱と無秩序とエゴと暴力。それらすべてが激しく混ざり合っていた。そしてその中心には、真っ赤な炭の上を悠然と歩く男たちがいた。
燃えているのはインドそのものだった。
なんて面白い国なんだ、ここは。腹の底からそう思える夜だった。
ところで、このアイヤッパの火渡りには、エピローグとでも呼ぶべき話がある。
火渡りの夜から二日後の朝のことである。そのとき僕はマフブババードから100kmほど離れたワランガルという町の食堂で朝食を食べていた。いつものようにワラというソース付きのドーナツを食べ、食後に甘いチャイを飲んだ。そのときだった。隣のテーブルに座っていた男が、不意に声を掛けてきたのだ。
「イッツ・ユー?」
彼はたどたどしい英語でそう言うと、読んでいた新聞を広げて見せてくれた。確かにそこには僕の顔写真が載っていた。
「イエス! イッツ・ミー!」
僕は驚いて言った。それは火渡りについて書かれた記事だった。たぶん僕にカメラのスペックを詳しく訊ねていたあのカメラマンが書いたものなのだろう。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| カラー刷りの新聞。(2)の写真の左に立っているのが僕だ |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
おかしかったのは、肝心の火渡りの写真よりも、僕の顔の方が大きく扱われていることだった。彼が持っていた安いデジカメでは、夜の祭りがうまく写らなかったのかもしれない。それとも祭りそのものより「日本人が見に来た」ということの方がニュース・バリューが高かったのだろうか。
新聞に顔写真が載ったことで、この日は行く先々で声を掛けられた。中には「一緒に写真を撮ろう」とカメラ付き携帯電話を向けてくる男もいたりして、ちょっとした有名人気分を味わうことができたのだった。
|
|