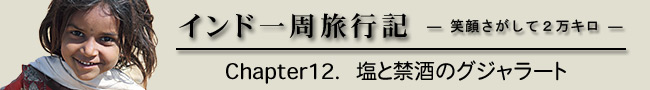|
 |
|
|
 |
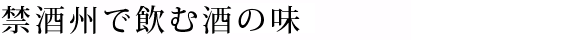 |
 |
 |
グジャラート州は酒飲みには辛い土地である。ここはインドで唯一の「禁酒州」、つまり州内でアルコール類を販売することが法律で禁止されているのだ。
僕は旅のあいだはたまにしか酒を飲まないので、グジャラートが禁酒州であることを知ったのは、州に入ってから数日後のことだった。町で酒屋を見かけないことには気付いていたのだが、酒の販売に厳しい制限を設けているインドでは珍しいことではなかったので、さほど気にしてはいなかったのである。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| グジャラート州独特の乗り物であるピックアップ・バイク。リアカーをアメリカンスタイルの大型バイクで引っ張るかなりワイルドな乗り物である。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
「グジャラート州にはアルコールを売る店はひとつもありません」
と教えてくれたのは、バウナガールという町のアイスクリーム屋で働く若者だった。その店は幅広い年齢層が集まる人気店で、子供や若者だけでなく中年のおじさんも美味しそうにアイスをなめていた。グジャラート州で「一杯やる」と言えば、飲み屋ではなくスイーツ店なのである。
「お酒は体に良くありません」と彼は言った。「飲み過ぎると頭がバカになります。あなたの国ではみんなお酒を飲むんですか? 信じられないな。だって日本人はとても優秀じゃありませんか」
「確かに飲み過ぎはいけないよ」と僕は反論した。「でも酒は人生を愉快にする。人付き合いを楽しくする。それに適量だったら酒は体に良いと言う人もいるんだ」
「まさか。ロシアでは酒の飲み過ぎで毎年何十万人も死んでいると聞きました。アルコール中毒になって自殺したり殺人を犯す人もたくさんいる。それでも酒が体に良いと言えるんですか?」
「・・・・」
返す言葉がなかった。彼の言い分はまったくもって正しかったからだ。酒の飲み過ぎは体に悪いし、人を愚かな行動に駆り立てる。それをわかっていながら、人は太古の昔から酒を飲み続けてきた。理由はわからない。理由なんてないのかもしれない。汝ただ酒を欲するものなり。
「君は酒を飲んだことがある?」
「もちろんありません。飲みたいとも思いませんね」
「酒の魅力は飲んでみないとわからないんだ」
負け惜しみみたいに聞こえたかもしれないが、それ以外に言いようがなかった。
「マンゴーを食べたことのない人に、マンゴーのおいしさを伝えることはできない。それと同じことだよ」
「でも、マンゴーは体に良い食べ物ですよ」
「・・・まぁ、そうだね」
僕の完敗であった。彼とはどうやっても乾杯できそうになかった。
彼のように頑なな人はさすがに珍しいが、インドには「飲酒は好ましくない習慣である」という価値観がどっしりと根を下ろしているのは確かだった。酒は享楽的で自堕落な不良が飲むもの、という考え方が特に保守的な田舎には強く染みついているのだ。これはイスラム勢力がインドを支配していた頃の名残だという話だが、詳しいことはわからない。
そのような価値観を反映しているからなのか、インドの酒屋は雰囲気がやたらと暗かった。酒飲みに対して罪悪感を感じさせる目的で作られているんじゃないかと思うほど、いかがわしい外観なのだ。
まず驚かされるのが酒屋全体を覆う鉄格子である。客が酔っぱらって暴れても、絶対に酒屋の中には入れないようになっているのだ。だからお客は商品を直接手にとって選ぶことはできない。客がパチンコ屋の景品交換所のような小窓から代金を突っ込むと、その代わりに古新聞に包まれた酒瓶が手渡されるという仕組みになっているのだ。店主が「旦那、これが例のブツですぜ」と言い出すんじゃないかと思うようなハードボイルドタッチの演出である。
酒屋を訪れる客もまともそうには見えなかった。社会の落ちこぼれとまでは言わないが、家庭や職場で深刻な問題を抱えていそうなやさぐれた感じの人が多い。もちろん女性客は皆無だった。
そのような後ろめたい思いをして手に入れたインドの酒は、残念ながらひどい味だった。もちろん高い金を出せばそれなりに美味しい酒もあるのだろうし、金持ちは外国産のウィスキーなどをたしなんでいるようだが、庶民が飲む安酒ははっきり言ってまずかった。人工的なアルコール臭が鼻につく、明らかな粗悪品なのだ。スプライトやコーラで割って、味をごまかさないととても飲めたものではなかった。
僕は酒にうるさい人間ではない。ワインの産地にもこだわらないし、ウィスキーの微妙な風味の違いにも頓着しない。気持ち良く酔える酒ならまず満足できるというタイプの人間である。その僕がまずいというのだから、本当にまずいと思っていただいていいだろう。
しかもインドの安酒はまずい上に高いのだ。一番手頃なウィスキーの小瓶が50から60ルピーほど。ビールは一本40ルピーほどである。平均的な肉体労働者の日給が50ルピーから100ルピーであることを考えると、これはかなり高額である。貧乏人は酒など飲むな、という無言の圧力を感じる価格設定なのだ。
バーも暗い。インドのホテルには地下室をバーにしているところが多いのだが、どこも洞窟のような暗さなのである。暗すぎて手元のメニューが読めないぐらいだ。もちろんこれはロマンティックなムードを演出しようとしているわけではない。なにしろ客も従業員も男ばかりなのだ。インドには男女が仲良くなるためのお酒というものは存在しないし、「酔った勢いで○○しちゃった」なんてこともないのである。
女がいなくても、洞窟のように暗くても、酒を飲む男たちは楽しそうだった。一人で静かに飲んでいる人はほとんどいない。たいていは友達同士でぱーっと楽しく飲んでいた。バーや酒屋で見慣れない外国人がいると、気さくに声を掛けてくる人も多かった。
隣のテーブルで飲んでいるおじさんから、「こっちへ来いよ」と手招きされたので行ってみると、いきなり肩を抱かれてほっぺたにブチュっとキスされたこともあった。硬いヒゲが頬に当たってチクチクした。困った奴だ。酔うとキス魔になる人はインドにもいるらしい。
「エク・キス!(も一回キスさせろ!)」
オヤジはニコニコ顔で言うので、慌てて逃げた。勘弁してくれよ。ひょっとしたら「そっち」の気があるのかとも思ったが、たぶん単にフレンドリーな男なのだろう。インドでは男同士が手を繋いだり抱き合ったりするのは当たり前である。
ところで、禁酒州であるグジャラートを旅するあいだ、一度だけ酒を飲む機会があった。それはディウという長さ10キロほどの小島を訪れたときのこと。ディウ島は長年ポルトガルの植民地だったこともあって連邦直轄地域に指定されており、グジャラート州の法律が適用されていないので、治外法権的に酒の販売が許されていたのだ。
ディウ島の先端にはポルトガルが築いた堅固な要塞があり、町並みは植民地時代の面影を色濃く残していた。砦から見える海はとても静かで、風も穏やかだった。午後にはどの店もシャッターを下ろし、町は眠り込んだように静かになったが、これは植民地時代に持ち込まれたシエスタの習慣が今も残っているためだという。
ディウ島はまったくインドらしくない町だったが、そこで手に入れたウィスキーは極めてインドらしい味だった。要するにとてもまずかったのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|