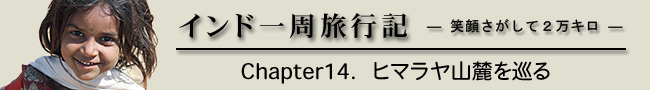|
|
|
 |
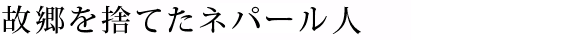 |
 |
 |
ロールの町からパバール川に沿って進む州道10号線を走って、ウッタラカンド州へ向かった。最低でも100キロは進みたいところだったが、午後から降り始めた雨で、予定が大きく狂ってしまった。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| ウッタラカンド州の山奥で出会った牛飼いの少年。まだ6,7歳なのにたった一人で牛を追っていた。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
雨宿りのために立ち寄ったサウラ村は、州道沿いに食堂と雑貨屋とバイクの修理屋が並んだだけの小さな集落だった。僕は食堂でチャイを頼み、火が入ったかまどの前で両手をこすり合わせて暖を取った。ただでさえ寒いのに、雨によってさらに体が冷えてしまっていた。
「こんなに寒くなったのは、3日前からですよ。それまでは暑かったんです。今年の天候は異常ですよ。いつもならこの時期にこんなに冷え込むことはないんです」
僕と同じように食堂で雨宿りをしていた男が流ちょうな英語で教えてくれた。ヴィシャンベル・ジョシさん。森林保護の仕事をする公務員だ。口ひげのせいで老けて見えるが、まだ28歳だという。
「地球温暖化の影響でしょうか?」
「さぁ、それは簡単に結論が出せる問題ではありませんが、その疑いは強いですね。とにかくこの寒さは農家に悪い影響を与えます。リンゴが大きく育たないんです」
ジョシさんによれば、ウッタラカンド州の人口の8割が農業に従事しているという。小麦やジャガイモの他にリンゴなどの果物も作っている。しかし産業として伸びているのは観光業と発電事業で、特にヒマラヤの豊富な雪解け水を利用した水力発電は、遠く離れた首都デリーへも電力を供給するほどだという。
しかしこの村の住民たちは、地元のダムが生み出した電気の恩恵をまだ十分には受けていない。電気は2年前にようやく通ったものの、使えるのは一日のうちの数時間に限られているし、まったく使えない停電デーもある(僕が訪れた日はたまたまその停電デーだった)。それでも村人は電気がない生活に慣れているので、あまり不便には感じていないようだ。電気は「使えたらラッキー」という程度のもので、大半の家はテレビを持っていなかった。しかし充電の効く携帯電話は半分以上の人が持っていた。
「日本ではお金を出して酸素を買う人がいるというのは本当ですか?」
ジョシさんは真面目な顔で言った。雑誌か新聞にそういう記事が載っていたらしい。「酸素バー」のことだろうか?
「そういう人も稀にいるみたいですね。でも僕は買ったことはありません。酸素が不足しているわけじゃないから」
「それじゃロボットのアザラシをかわいがる老人の話は?」
「それも本当だけど、数はすごく少ないですよ」
外国のメディアが取り上げる日本の話題はこの手のものが多い。ハイテク先進国で働くオタク趣味の人々。老人ホームのロボットアザラシも、酸素バーもそういう文脈に沿ったトピックだ。しかしこういうキワモノ的ニュースばかりが取り上げられることで、見る側の日本人像にバイアスがかかるのは避けられないだろう。
もちろん日本のメディアだって状況は同じようなものだ。日本のニュース番組で伝えられるインド人の多くは、何十年も飲まず食わずで生きているという老人や、目に唐辛子を塗り込んでも大丈夫だと豪語するおじさんのようなキワモノたちなのだから。
よく言われることだが「犬が人間に噛みついてもニュースにならないが、人間が犬に噛みついたらニュースになる」。ニュースバリューとはそういうもので、だからこそ僕らはそれを勘定に入れた上でニュースを見る必要があるのだろう。
午後3時半になっても雨は止まなかった。とりあえずの目的地にしていたチャクラータの町は、ここから45キロ離れているという。そのあいだに宿は一軒もない。町らしい町もない。だから雨の中を45キロ(道が悪いので3時間近くかかるだろう)走り続けるか、それともこのサウラ村にとどまるかを、今すぐに決める必要があった。サウラ村にも宿屋はないが、希望すれば部屋を融通してくれる臨時の民宿みたいな家があるという。
しばらく考えてから、この村に泊まることに決めた。雨脚がさらに強まる危険性もあったから、安全策をとるべきだと判断したのだ。
案内されたのは本当にごく普通の民家だった。普段は子供たちの寝室になっているらしく、ベッドが二つ置かれているだけのシンプルきわまりない部屋だったが、不満はなかった。どうせ寝るだけなのだ。雨がしのげて、安全が確保されているのなら、それ以上の贅沢は望まない。用を足すときは外の共同便所を使うようにと南京錠の鍵を渡された。宿代は100ルピーということで話がまとまった。
少し昼寝をしてから、傘を差して村の中を歩いた。住民の中には日本人に似たモンゴロイド系の顔の人が多かった。
ジョシさんによれば、この村は隣国のネパールから移住してきた人が人口の4割を占めているという。30年ほど前から、貧困や政治的混乱に耐えかねたネパール人が国境を越えてインドに流入してくるようになったのだが、そうした難民の一部がこの村に定住したのだ。
難民の子供たちの世代、つまりネパール系2世の若者たちはネパールという国を知らない。インドに生まれ、インド国籍を持ち、ヒンディー語を話し、一度もネパールを訪れたことのない彼らにとって、ネパールはすでに母国ではなく、「近くて遠い外国」になっているのかもしれない。
ネパール系の若者のひとりが携帯電話に入れているインドポップスのミュージックビデオを見せてくれた。インドの町には携帯電話用の音楽ファイルやミュージックビデオをダウンロード(もちろん違法コピー)してくれる店があるので、たとえテレビやラジカセがなくても、最新の音楽やダンスを楽しむことができるのだ。
彼の携帯電話に入っていたビデオファイルはインドポップスと地元ウッタラカンドの民謡ばかりで、ネパール音楽はひとつもなかった。インドではネパール音楽のCDやビデオがあまり流通していないという事情もあるのだろうが、彼自身みずからのルーツであるネパールの文化にあまり興味がないようにも見えた。
|
|
|
僕が「いつかネパールに行ってみたい?」と訊ねたときも、返事は「ノー」。実にそっけなかった。
「貧しい国です。いまだにまともな政府ひとつ作れない」
その通りだ。おそらく両親や仲間たちからそう聞かされているのだろう。経済的にも政治的にもインドより劣るちっぽけな国。
でもネパール人の口からそんなセリフを聞きたくはなかった。ネパールは確かに貧しい国だけど、美しいものもたくさんある。僕は実際にこの目でそれを見てきたのだから。
釈然としない思いを抱いたまま、村はずれまで歩いた。そこには大きな谷があり、斜面に沿うように段々畑が広がっていた。長い時間をかけて人が作り上げた優美な曲線。何度見ても心を動かされる風景だった。谷を挟んだ向かい側には小さな集落があり、石造りの家から炊事の煙が上がっていた。やわらかく降り続く雨に覆われて、すべての景色は遠い記憶のように色あせ、ぼんやりとかすんでいた。
故郷を出たネパール人たちが、なぜこの土地を選んで住み着いたのかがわかるような気がした。ここはあらゆる点でネパールに似ているのだ。ヒマラヤ山麓の自然も、牛を使って段々畑を耕すやり方も、質素な暮らしぶりも。
彼らは経済的、政治的な理由でネパールを捨てた。けれど山の民であることは捨てられなかったのだ。
夕食はネパール人の男が一人で切り盛りする食堂で食べた。炊き立てのご飯と豆スープとカリフラワーのカレーと生タマネギ。ご飯はネパールと同じように圧力鍋で炊かれていた。味付けもネパール風。素朴で温かみのある味だった。
夕食と一緒にネパールの焼酎「ロキシー」を飲んだ。インドでは酒に高い税金がかけられているので、安物の酒でもけっこう値が張るのだが、ここのロキシーはネパール人が無許可で作っている地酒なのでとても安かった。1リットルがたったの20ルピー(40円)。驚くべき安さだ。
アルミコップに注がれたロキシーは、ネパールの山村を旅したときに毎日のように飲んでいたものとまったく同じ味だった。アルコール分は少ないが、クセのない素直な味。シコクビエから作られた本物のロキシーに間違いなかった。
一人で飲むにはちょっと量が多すぎるなぁと思っていると、その気持ちを察したかのようにネパール系の若者たちがぞろぞろと集まってきた。誰も英語が話せなかったので、最初はもじもじしていたが、僕が知っているネパール語をいくつか披露して、「さぁ飲めよ」とロキシーをグラスに注いでやると、すぐに打ち解けた表情になった。
何を話したわけでもないし、何か特別なことがあったわけではない。でもこうして一緒に酒を飲んでいるだけでなんとなく通じ合う部分があった。そういう感覚もネパール人ならではのものだった。人当たりがやわらかくて、シャイで、すべてにおいてマイルドなのだ。インド人のような「オレがオレが」的自己主張の強さがない。そういうところが日本人にも似ていて、なんだかほっとできるのだった。
|
|
|
ロキシーの入ったペットボトルが空になる頃には、食堂はすでに店じまいを始めていた。まだ8時を過ぎたばかりなのだが、この村では「夜更け」なのである。出歩く人の姿もなく、村はしんと静まり返っていた。今日が電気の来ない停電デーなのも関係しているのかもしれない。
持ってきた懐中電灯で足元を照らしながら部屋に戻った。棚に置いてあるロウソクにライターで火をつけてみたが、そのか細い明かりだけでは部屋の隅っこは暗いままだった。
ベッドに潜り込んで天井を見上げた。月面のように静かだった。ときどき遠くから犬の吠える声が聞こえたが、それ以外の物音はまったくなかった。
ロキシーの酔いが心地よく全身に回り始めていた。目を閉じるとすぐに眠気がやってきた。
|
|