|
 |
|
|
 |
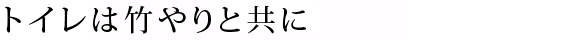 |
 |
|
「トイレに行きたくなったら、これを持っていきなさい」
そう言って村長が手渡してくれたのは、先を尖らせた太い竹だった。太平洋戦争末期に「本土決戦」を覚悟した女性が持たされたような竹やりが、なぜ用を足すときに必要なのだろう。ひょっとしたら、これで尻を拭けということなのだろうか。日本でも、紙で拭くようになる前は竹のヘラでこそぎ落としていたっていうからな。
村長に目的をたずねてみると、意外な答えが返ってきた。
竹やりは豚を突くためのものだというのだ。この村の豚は人間のウンチが大好物で、用を足そうとズボンを下ろしてしゃがみ込んだだけで、「お、ご馳走が出てくるぞ」とばかりにその人の周りに集まってくるというのだ。中にはまだモノを出さないうちから尻をなめ回すヤツもいるらしい。要するにこの竹やりは背後から迫ってくる豚を突き、ヤツらがひるんだ隙に用を足すためのものなのである。
しかし「竹やりで豚を追っ払いつつ用を足す」なんて器用なことが僕にできるんだろうか?
不安な気持ちを抱きながら、僕は村はずれにひとつだけある高床式のトイレに向かった。実はこのトイレはNGOの指導のもとで数ヶ月前に新しく作られたもの。それまでは屋外で、それこそ竹やりで豚を追い払いながら慌ただしく用を足さなければいけなかったのだが、今は一応壁で仕切られた個室で落ち着いて用が足せるようになっていた。
それでも豚はやってきた。僕がトイレに入るやいなや、その気配を察知した豚の親子が猛然と駆け寄ってきたのだ。高床式のトイレは部屋の真ん中に四角い穴が空いていて、そこから排泄物が地面に落下するというきわめてシンプルな作りになっているのだが、その豚の親子は「もう待ちきれない!」といった感じで、ブヒブヒと鼻を鳴らしながら穴の下から僕の尻を見上げているのである。す、すごい。噂通りとんでもなく貪欲な豚である。
僕は通常、お通じのよい方である。便秘になることはほとんどない。それは僕が誇れる数少ない特性のひとつなのだが、この時ばかりはさすがにひねり出すのにかなりの時間を要した。誰かに排便を見られるというのは、しかも下から「見上げられる」というのは初めての経験だったからだ。しかも豚の目は真っ赤に血走っていて、「おい、早くしろよ」といきり立っているのだ。前足を思いっきり伸ばして、鼻先を尻にくっつけんばかりの勢いなのである。
僕は村長に渡された竹やりで豚の鼻面を突いた。ここで一発ぶちかましておかないと、図に乗った豚に尻を舐められそうだったからだ。しかし豚はめげなかった。すぐにまた鼻面をぐいっと近づけてくる。
くそ。僕は再びやりを手にして、今度は思いっきり突いた。その一撃でさすがの豚も意気消沈したのか、しばらくはおとなしくしていた。ざまぁみろ。こうしてようやく落ち着いて用を足すことができたのである。
豚は僕が落としたモノをまたたく間に平らげてしまった。よほどお腹が空いていたのだろう。すさまじい食欲だった。豚はなんでも食う動物だと言われている。残飯であっても人糞であってもお構いなし。そんな雑食性の動物であるがゆえに、ある地域では非常に便利な家畜として重宝され、ある地域では汚い生き物として忌み嫌われている。そんな話を知識として知ってはいたが、実際にこうして「ウンチを食べる豚」を目にすると、なるほどあの話は本当だったんだなぁと妙に感心してしまった。
豚が処理するトイレ。それは究極のエコトイレでもあった。人糞を食べた豚が肥え太り、その肉を人が食べるわけだから、無駄なものが一切出ないわけだ。
人間も豚も同じように食べ、同じようにウンチをひねり出し、生きて、そして死んでいく。その意味では平等なのだ。人間だけが循環する自然の輪から外れた特別な存在だと考えるのは、単なる思い上がりにすぎないのではないか。豚のトイレはそんなことを教えてくれたのだった。
夕方になると、村人たちが伝統の踊りを披露してくれた。男たちが「プロン」という竹とひょうたんで作った楽器を吹き、民族衣装で着飾った女たちが一列になって踊る。プロンの作り自体はかなりちゃちなのだが、30人もの男たちによって一斉に奏でられる音は、幾重にも重なり合って、パイプオルガンのような深みを持って村中に響き渡っていた。
この踊りが意味するところは長老にもわからないという。元々は何らかの意味があったのだろうが、ある時点で忘れ去られてしまったのだろう。ムルー語には独自の文字もあるのだが、それは代々村長をつとめる一家にだけ伝えられてきたので、天災が起これば失われてしまう危険がある。実際、3年前には焼き畑の火が原因で起こった大火事によって、ほとんどの家が焼失してしまったのだそうだ。
夜には、村の男たちと一緒に酒を飲んだ。電気のない村は、夜になると真の闇に包まれるから、楽しみといえば酒を飲むことぐらいなのだろう。山岳民族の多くがそうであるように、ムルー族も酒好きである。人口の8割をムスリムが占めるバングラデシュでは、外国人以外の一般人が酒を買うのはとても難しいのだが、少数民族が自家製の酒を売り買いすることは例外的に黙認されている。
僕らがバンドルボンの町で手に入れた米焼酎は500mlで400タカ(480円)と、この国の物価水準からすればかなり高額なものだった。しかもまずい。アルコール臭さばかりが鼻につく酒で、何かで割らないととても飲めないような代物だった。
それでも村人たちはこの粗悪な焼酎をストレートでぐいぐい飲み、ほろ酔い気分になって歌をうたいはじめた。抑揚のない単調なメロディーで、しかも部屋の真ん中に置かれたランプの炎の前で歌うものだから、なんだか怖かった。ゆらゆらと揺らめく炎に照らされた男の顔は、必要以上に陰影が強調され、怪談を語る稲川淳二のような迫力を感じさせた。
しかしこの歌は、意外にもラブソングだった。
「僕は君と結婚したいのだけど、今はお金がない。愛しい君よ、もう少し待ってください」
だいたいそんな意味だという。そう、「姉さん女房婚」を受け入れるために、男たちは持参金を貯めなければいけないのだ。その苦労を歌に込めていたのである。
ムルー族の男たちはとてもシャイで警戒心が強い。外国人と積極的に関わろうとはしないし、我々の様子を少し離れたところからそっとうかがっている人が多い。女たちが豪放で開けっぴろげな分、男たちは「しおらしい」のだ。うまくバランスが取れているものだと思う。そんな男たちの警戒心も酒が入るとあっさりと緩んでしまうのが面白かった。
つかの間の宴が終わると、あたりはしんと静まりかえった。ときどき家畜が鳴く声が聞こえるだけだった。
村人は日が昇ると目を覚まし、日が暮れると眠る。何十万年ものあいだ人類が繰り返していたであろうシンプルな暮らしがここにはあった。
外は満天の星空だった。天頂にオリオン座がぴたりと貼り付き、空をふたつに分けるように流れる天の川がはっきりと見えた。目が慣れてくると、砂粒のように細かい星までが浮かび上がってくる。さっきまでそこにあったはずの星座が見えなくなるほど、あまりにもたくさんの星が空を埋め尽くしていた。
|
|
|
|
