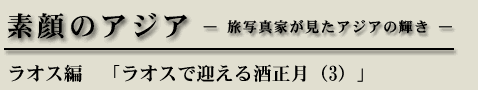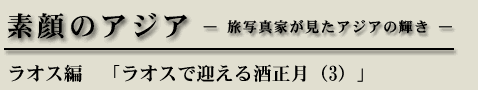|
|
|
|
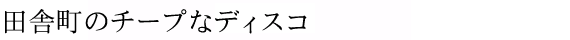 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| ディスコの天井から吊り下げられたCDがチープ感を誘う |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
高校生たちと杯を酌み交わした後、彼らと一緒にディスコに行った。ラオラーオを飲んで酔っぱらうと、ディスコに行って踊るのが定番なのだという。娯楽の少ない町の中で、若者たちが有り余るエネルギーを発散できる場所は、ディスコぐらいしかないのだろう。
もちろんラオスの田舎町のディスコが洗練されたものでないことぐらい承知していたのだが、そのディスコは予想以上にひどかった。まず驚いたのは音の大きさだった。フロアの壁には巨大なスピーカーが置かれているのだが、それをフルボリュームで鳴らしているので音は割れ、もはやそれが音楽なのか、工事現場の音を拾ってきて再生しているのか、よくわからないような状態だったのだ。
インテリアもひどかった。一応天井には小さなミラーボールがクルクルと回っているのだが、その光はとても弱く、煌びやかさが足りないので、それを補うために不要になったCDを何十枚もぶら下げていたのである。ミラーボールの光を反射したCDは七色に光って煌びやかではあるのだが、そのチープ感はいかんともしがたかった。マンションのベランダに吊されたカラス除けを思い出してしまった。
ディスコの中の高校生は意外にもおとなしかった。せっかく男女十人が集まっているというのに、男は男同士で、女は女同士でかたまっているのだ。もちろん男女ペアになって体を寄せ合って踊るということもなかった。酒に対しては早熟だけれど、恋愛に関しては奥手ということなのだろうか。
そんな中で、一人の女の子が突然プラスチックの椅子の上に登って、踊り始めた。酔っぱらっているらしく、手を振り腰をくねらせて大胆に踊っている。まさにお立ち台ギャル状態。扇子があったら渡してあげたかった。
他の女の子たちは手を叩き口笛を吹きながら彼女を盛り上げていたが、男の子たちはあんぐりと口を開けてその踊りを眺めるばかりだった。どうやらラオス人女性は、酒を飲むと豹変するという性質を若いうちから備えているようだった。
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| ラオスで見かけた自転車のサドルには「にきです」の文字。って言われても・・・。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
とにかく酒ばかり飲んでいた一日だった。勧められるままにラオラーオを飲み、頃合いを見計らって、「コープチャイ(ありがとう)」と言っておいとまするのだが、すぐに別のグループから「こっちにも来いよ」と声が掛かった。川海苔や焼き芋なんかをつまみながら酒を飲み、歌をうたい踊りをおどる。
そんなことを延々と繰り返すうちに、少しずつ飲んでいたはずのラオラーオが徐々に効き始め、足元がふらついてきた。決定打は浴びていないのだが、初回から細かいジャブをもらい続けてきたボクサーみたいだった。頭では「まだまだいける」と思っているのだが、足が言うことを聞かないのだ。
とにかく宿に帰らなくっちゃな・・・。
そう思って歩き出したところで、僕の記憶はぷっつりと切れてしまう。ブラックアウトだった。
目が覚めると真っ暗な部屋の中にいた。宿のベッドの上だった。腕にはめたままの時計を見ると、夜中の1時を指していた。最後の記憶が夕方の5時頃だったから、それから8時間も眠り続けていたらしい。
体を起こすと、頭が鈍く痛んだ。服は着たままだし、コンタクトレンズだって外していない。たぶん、ふらつく足で何とか宿に帰り着き、そのまま倒れ込むようにして眠ってしまったのだろう。そういう状況証拠だけは残っているのだが、肝心の記憶が全くない。コンピューターをシャットダウンしたように、記憶が途絶えてしまっている。
教訓。ラオス人の宴会のペースに巻き込まれていては、とても体が持たない。何しろ彼らは高校生の頃から40度の強い酒に慣れ親しんでいる人々なのだ。しかも僕はいくつもの宴会を掛け持ちしなければいけなかった。最初からこうなることは目に見えていたのだ。何とか自力で宿に帰り着けただけ、幸運だったと言うべきだろう。
まだ午前1時だというのに、外では鶏が鳴き始めていた。やれやれ、このあたりの鶏は朝が早いらしい。一羽が鳴き始めると、町中の仲間がそれに呼応して大合唱を始めるのが鶏の習性なのである。一度鳴き始めると誰にも止められないのだ。
僕はその大合唱をやり過ごそうと、二日酔いの頭に枕をかぶせてうずくまった。鶏たちはまるで個人的な嫌がらせのように、いつまでも鳴き続けていた。
|
|