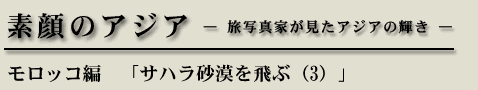|
 |
|
|
|
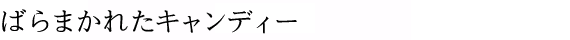 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| マラケシュのスーク(市場)はエキゾチックな場所だ。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
日本人にとって、モロッコは比較的マイナーな部類に入る国だけれど、ヨーロッパ人のツーリストには非常にポピュラーな観光地である。地図を開いてみれば一目瞭然なのだが、ヨーロッパに一番近い異文化圏――つまりイスラム圏――の最前線に位置するのがモロッコなのだ。
モロッコを訪れる外国人の中で、最も多いのがフランス人である。モロッコはかつてフランスの植民地だったこともあって、フランス語がかなり通じるのである(その代わり英語はほとんど通じない)。
その次に多いのはスペイン人。何しろスペインとモロッコを隔てているジブラルタル海峡は、最も狭いところでわずか14キロしかないのである。お隣さんの気楽さで言えば、日本から見た韓国以上のものだろう。
ヨーロッパ人観光客のお目当ては、まずマラケシュやフェズなどの古い街である。僕らもマラケシュの旧市街は散々歩き回ったが、何度歩いても道に迷うほど入り組んでいて、飽きることがなかった。スーク(市場)で売られているのもユニークでカラフルなものばかりだったし、ジャマ・エル・フナ広場の大道芸人たちも個性豊かだった。マラケシュでは毎日がお祭り騒ぎだった。
古い街と共に旅行者を惹きつけているのがサハラ砂漠である。僕らも超軽量飛行機に乗ってサハラ上空を飛んだり、オアシスの町を歩いたり、月面のような荒涼とした場所で暮らす人々と出会ったりしたが、その印象はマラケシュの街よりもずっと強かった。自然の厳しさと人々の逞しさをこれほど強く感じられる場所はそうはないだろうと思った。
サハラ砂漠ではひどい目にも遭った。サハラに到着した夜、原因不明の腹痛と嘔吐に苦しんだのである。それは夜中の2時頃に突然襲ってきた。それから夜が明けるまで、僕は何度も何度も吐き続けた。最後には吐くものが無くなって、胃液しか出てこなくなったのだが、それでも吐き気は収まらなかった。こんな経験は初めてだった。羊肉にあたったのではないか、というのが医者の見立てだった。そんなわけで、僕にとってのサハラ初日は、宿のベッドの上でじっと横になって過ごす羽目になったのである。
サハラ二日目には、体調も回復してきたので、予定通りレンタカーで砂漠を走り回った。遊牧生活を送っている家族を訪ね、彼らに話を聞いた。観光客に慣れている人もいれば、全く慣れていない人もいた。慣れている人の方が取材は進めやすかったが、僕は彼らにあまりいい印象を持たなかった。観光客に慣れた人たちは、僕らのことをお金をくれる存在としてしか見てくれなかったからである。
僕らが求めていたのは、外国人に愛想良くしてくれる人ではなく、自分の言葉でここでの暮らしぶりを語ってくれる人だったのだが、そのような人を見つけるのはとても難しかった。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 砂漠に住む遊牧民の前で、得意のジャグリングを披露するウィリアム。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
一台のピックアップトラックが砂煙を上げながら近づいてきたのは、僕らがある遊牧民の一家にインタビューを試みようとしているときだった。そのピックアップトラックには5人の女性が乗っていた。運転席と助手席に中年の女性が座り、荷台には三人の若い女性が乗っていた。話し言葉からすると、スペイン人のようだった。
驚いたのは彼女たちの服装だった。5人ともが揃って露出度の高い格好をしていたのである。一番若い子なんか、少しうつむけばバストが見えそうなほど大胆に胸元の開いたタンクトップと、お尻が半分見えているような短いショートパンツというスタイルだった。
スペインのリゾート地では、それぐらいの露出は当たり前なのかもしれない。しかしここはイスラムの習慣を堅く守るモロッコである。女性が腕や足をほんの少し見せただけでも「はしたない」とされるような土地なのである。
そのスペイン人の服装には、自分たちが異国に来ているということ、異文化に取り囲まれているということに全く無自覚であることが表れていた。自分さえ気持ち良ければ周りがどう思おうが関係ない、という傲慢な態度がミエミエだった。
その5人組は砂漠で道に迷ってしまったので、僕らに道を尋ねようと近づいてきたようだった。僕らのガイドは彼女たちの地図を見ながら、行き先を指示してやった。どうして彼女たちが右も左もわからない砂漠をガイドも付けないで走り回っているのか、そのことも理解できなかった。
遊牧民の母親が子供たちの背中を叩いたのは、そのときだった。
「ほら、何をぼーっとしているんだい。早く行きなさい!」
と母親は5人組の方を指さした。子供たちは弾かれたように5人組の元へ駆け寄った。そしてポケットからネックレスやスカーフなどの土産物を取りだして、「買ってよ!」「買ってよ!」の大合唱を始めた。
5人組はその大合唱には取り合わなかった。既に他の場所で何度もお土産攻撃にさらされていて、とことんうんざりしているのよ、という顔をしていた。その気持ちは僕にもわかる。持って帰ったところで何に使えばいいのかわからないようなチープなお土産は、ひとつ買ってしまえば十分だから。
荷台に座っていた三人が、バッグの中から大量のキャンディーを取り出したのは、運転を担当していた女が再び発進しようとエンジンをかけたときだった。
三人は何十個ものキャンディーをそれぞれの手に掴むと、それを地面にばらまいた。赤や青や黄色のキャンディーの包み紙が、砂の上にバラバラと落下した。それを見た遊牧民の子供たちは、競い合うようにキャンディーを拾い始めた。三人はバッグに手を突っ込んで、再びキャンディーをまいた。子供たちはそれをまた奪い合った。そして全てのキャンディーが拾われるのを見届けないまま、ピックアップトラックは砂塵を巻き上げながら走り去っていった。
僕はその様子を呆然と眺めていた。醜い光景だった。もちろん子供たちが、ではない。スペイン人たちが、である。それはまるで動物園のワニに餌をやるような態度だった。そのあまりにも傲慢な態度に、僕は胃袋の底から昨日の嘔吐感が蘇ってくるのを感じた。
友好の印として子供にキャンディーをあげること自体は、悪いことではないと思う。僕も旅先で仲良くなった子供に、お菓子や食べ物を分けてあげたことは何度もある。
問題はその方法だ。モノをあげるときの気持ちなのだ。スペイン人の女たちは、ピックアップトラックの荷台という高みから、子供たちを見下ろしていた。そして上からの目線のまま、キャンディーを放り投げ、地面に落ちたものを拾わせた。
もし彼女たちが子供にキャンディーをあげたいと思ったのなら、車を降りて直接手渡せばいいのだ。それが人間としての最低の礼儀ではないか。どうしてそんな簡単なことができないのか、僕には全く理解できなかった。
旅行者自身の手によって、旅する土地が損なわれていく。これはその見本のような出来事だった。旅行者が行く先々で分別なくモノを与え、その土地に住む人々がそれを当然のこととして受け取る。旅行者が現地の子供を「モノを欲しがる存在」としてしか見なければ、そのお返しとして子供たちも旅行者を「モノをくれる存在」としてしか見なくなる。そのようないびつな関係が固定化されるとき、その土地は死ぬのだと思う。
観光客にスポイルされ、本来の魅力を失いつつある観光地を、僕はいくつも通ってきた。それは見るに堪えない光景だった。僕の足が次第に観光地から遠のくようになったのは、このような醜い場面に出くわしたくないという気持ちがあったからでもあった。
|
 |
|
|