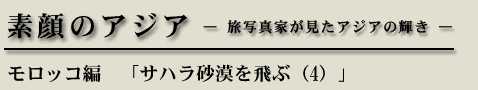|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
物乞いに対してお金をあげるべきか否か。これはアジアやアフリカを旅する外国人のほとんど全員が直面する問題である。特に物乞いがほぼ皆無という世界でも稀な国である日本から来た旅行者にとって、この問題は深刻かつナイーブなものだ。
僕はモロッコを旅する直前に、津波後のスリランカを旅していたのだが、そこでも物乞いにお金をあげるべきか否か、大変悩むことになった。結局、僕はお金をあげなかったのだが、その決断が正しかったのかどうかは、今でもわからない。
それはおそらく、「正しい」と「正しくない」とに明確に線引きのできる問題ではないのだ。答えはひとりひとりに委ねられている。そしてどのような行動を取ったとしても、後には気まずさと居心地の悪さが残るのである。
モロッコを一緒に旅したウィリアムは、僕とは反対にお金をあげる人だった。道端にうずくまる物乞いの老婆にも、観光客狙いのはすっぱな子供にも、分け隔てなくあげる。それが彼の基本方針だった。
あるとき僕はウィリアムに訊ねてみた。どうしてお金をあげるんだ、と。
「僕は貧しさというものを知っているから、あげずにはいられないんだ」と彼は言った。「子供の頃はとても貧しかったからね、物乞いの気持ちがよくわかるんだよ。僕が5歳ぐらいの時に、一家の収入が途絶えたときがあった。本当に1ドルの金もなくなって、隣に住んでいる人に『20ドル貸してくれませんか?』って頼みに行ったことがある。その時の気持ちは今でも忘れられないよ。とても惨めだった。物乞いはただ楽をして金を手に入れたいだけの怠け者だという人もいる。でも僕はそうは思わない。それぞれに事情があって、そうせざるを得ないんだ。5歳の頃の僕みたいにね」
貧困の辛さを身を持って知っているウィリアムは、その経験に基づいて物乞いにお金をあげていた。僕は彼のやり方を尊重したし、彼の方も僕がお金をあげないことについて自分の意見を押しつけるようなことはしなかった。
しかし一度だけ、僕とウィリアムの意見が対立したことがある。それは、アトラス山脈の山村を歩き回っているときに知り合いになった地元の女の子に、インタビューをしたときのことだった。
僕らは彼女の日常生活について訊ね、「お金持ちになったら何が欲しい?」とか、「外国へ行くんだったらどこがいい?」といった質問を投げかけた。はじめのうちは慣れない状況に戸惑っていた彼女だったが、会話を重ねるに従って徐々にリラックスしていった。
彼女は生まれてから22年間一度も学校に通ったことがなかったのだが、最近になって読み書きを教える学校に通い始めたのだそうだ。僕らが驚いたのは、彼女が自分の誕生日を知らないという事実だった。アメリカや日本のように誕生日を毎年祝うという習慣は、この土地にはないようだった。
僕らは彼女が入れてくれた紅茶を飲みながら話を続けた。モロッコの紅茶は、金属製のポットに注いだお茶をいったんグラスに注ぎ、それをまたポットに戻す、ということを何度か繰り返してサーブされる。グラスに注ぐときはポットを高く持ち上げ、泡を豪快に立てる。モロッコには「泡のないお茶は、コブのない駱駝と同じだ」という言い方があるという。泡はポットの中に入れた砂糖の塊を溶かすのを助け、味を豊かにするのだそうだ。
|
 |
|
小さな窓からは柔らかな光が射し込んでいた。それがはにかんだ彼女の表情を印象的に浮かび上がらせていた。僕は写真を撮ってもいいかと訊ねた。モロッコで女性を撮るのは非常に難しかったので、断られるのを覚悟の上だった。
しかし意外にも、彼女は恥ずかしそうなそぶりを見せながらも、「いいわよ」と頷いたのだった。会話を重ねるうちに、警戒心が解けてきたのだろう。僕がカメラを構えても、彼女はリラックスした表情のままでいてくれた。窓から射し込む光は申し分なかった。シャッターを切りながら、これはきっと美しいポートレートになると確信した。
僕らはお礼を言って、家を出た。彼女は玄関に出て、名残惜しそうな顔で見送ってくれた。滅多にやってこない外国人と過ごした時間は、彼女にとっても特別なものだったのだろう。
ウィリアムが彼女にお金を手渡したのはそのときだった。インタビューに応じてくれたことと、写真を撮らせてくれたことに対するささやかなお礼のつもりだったのだろう。金額は決して多いものではなかった。それでも、僕はその行為に強い違和感を覚えた。あの部屋の中で僕らが共有していたものが、それによって損なわれてしまったように感じたのだ。
僕が誰かに向けてカメラを構えるとき、そこには「あなたは特別な存在なんだ」というメッセージが込められている。他の誰でもないあなたに注目しているんだという意思を明確に伝えることによって、相手にも自分の存在に注目してもらう。
そのようにして被写体と向かい合う時、僕と彼(あるいは彼女)との間には、対等な関係が成り立つ。相手を見下ろしたり、見上げたりすることなく、同じ時間を共有する人間同士としてまっすぐに向かい合う。何気ない日常の中に美しい光が宿るのは、そのような瞬間なのだ。
しかしそのような対等な関係はとても壊れやすいものでもある。モノやお金を渡すことによって、一瞬にしてその関係が変質することだってある。「何かあげる」という行為には、それだけ強い力があるのだということを自覚しなくてはいけないのだ。
僕はそのような自分の考えを、なるべく正直にウィリアムに伝えた。僕の英語力で微妙なニュアンスを伝えるのは至難の業だったけれど、最後には彼も僕の言わんとしていることを理解してくれた。
「君の言う通りかもしれないな」と彼は言った。「彼女はお金を欲しがっているわけではなかった。僕らとの会話を楽しんでいた。そのことに気付かなかったのは、明らかに僕のミスだよ」
ウィリアムは自分のポリシーに自信を持っていたけれど、過ちがあればそれを素直に認めることができる男だった。そして、そこから何かを学ぼうとする謙虚な姿勢を持っていた。彼の最も尊敬できる点は、そんな度量の広さだった。
モロッコでの二人旅を通じて、僕は多くのことを経験したけれど、最も刺激的だったのは他でもないウィリアムという男とのぶつかり合いだった。何か問題が起こるたびに、僕らは話し合い、より良い方法を探ろうとした。プロジェクトそのものについても何度も話し合った。
育ってきた環境も文化も言葉も違う相手とコミュニケートするのは決して簡単ではなかったが、僕らはその困難さを楽しんでいたように思う。
それは僕らにとってとても長い1ヶ月だったが、同時にとても密度の濃い1ヶ月でもあった。
|
|
|
|
|
|
|