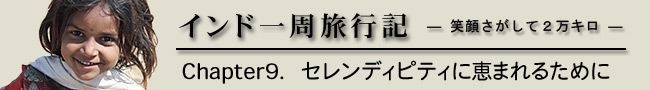|
 |
|
|
 |
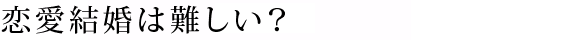 |
 |
 |
マディヤ・プラデシュ州にあるビチヤという町でも、幸運な出会いが待っていた。
例によって、僕はビチヤという町に関する情報を何ひとつ持たなかった。悪夢のようにひどい道をひたすら走り続けて、「もうこれ以上進むのはごめんだ」と思ったところに現れた辺境の町だった。
町の人に宿はないかと訊ねてみると、バス乗り場の近くに一軒あるという。こんな辺境の町にもちゃんと宿があることに驚きながら訪ねてみたのだが、そこはインドでも屈指のひどい宿だった。シングルベッドがギリギリ収まるだけのスペースしかない極狭の部屋。窓がなく、天井からぶら下がる裸電球もひどく暗い。まさに独房の趣であった。もちろんバスルームは共同で、これがまたすさまじく汚い。掃除なんてまったくしていないのだろう。
受付に座っているのも暗い顔をした中年男だった。部屋代は100ルピー(200円)だという。安いことは安いが、こんな心が寒くなる宿に一泊するぐらいだったら、他の町を当たってみた方がはるかにマシだと思った。
僕は重い足取りで宿を出て、バイクにまたがった。夜道を走る危険はなるべくなら避けたかったが、この際だから仕方ない。そう思ってスターターをキックしてエンジンをかけ、何の気なしに視線を上げたところに「HOTEL」と書かれた看板があったのである。なんだ、他にも宿があるんじゃないか。
もうひとつの宿「スリ・ガネーシ・ロッジ」はまともだった。清潔とまでは言いがたいが、そこそこ掃除もされているし、窓だってちゃんとあった。そしてインドの安宿には珍しく、若い女の子が受付に座っていた。ショービナという名前で、とてもきれいな英語を話した。去年カレッジを卒業したばかりで、今は公務員試験の勉強中なのだが、暇を見つけてはおばあさんが経営するこの宿の手伝いをしているという。
これまでの経験から、僕はインドの働く女性に対してあまりいいイメージを持っていなかった。銀行や鉄道の窓口やショッピングセンターなどで働く女性たちは、たいていひどく不機嫌そうに仕事をしていたからだ。愛想良くしたら減給にでもなるのかと思うぐらい、冷たくて不親切で無愛想だった。その態度はロシアやブルガリアなどの旧共産圏で働く女性公務員を彷彿とさせた。
しかしショービナは違った。ちょっとつっけんどんなところはあるけど、基本的にとても親切でにこやかだった。
「ここに外国人が泊まるなんて初めてなんです。アイ・アム・ベリー・ハッピー」
彼女はさわやかな笑顔で言った。インド女性からそんな言葉が聞けるとは夢にも思わなかったので、この宿に対する好感度は一気にアップした。一泊だけじゃなく二泊してもいいかな、なんて思い始めていた。男というのはまったく単純な生き物である。
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 宿題をやってこなかった罰としてこのポーズで立たされていた子供。ちょっと切ない表情がかわいい。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
ショービナは20歳だが、25歳まで結婚するつもりはないそうだ。今は公務員になるという目標を達成するのが先で、結婚はその後でも遅くはないと言う。保守的なインドの田舎にも、彼女のようなキャリア志向の女性が少しずつ増えているのだ。
そんな現代的なショービナでも、やはり恋愛結婚には抵抗があるらしい。インドでは親同士が決めた結婚「アレンジ婚」が普通だし、彼女も彼女の家族もそれを望んでいる。
「恋愛結婚は難しいことも多いんです」と彼女は言う。「私の叔母さんは恋愛結婚をしたんですけど、相手にはすでに奥さんと子供がいたんです。それでも彼女は結婚したわ。二番目の妻として。彼女は今でも最初の奥さんと一緒に住んでいるの。変だと思うでしょう? でもこのあたりではそれほど珍しいことじゃないの。そのあと叔母さんの家には三番目と四番目の奥さんがやってきたんだから」
インドでもヒンドゥー教徒であれば重婚は違法だが(ムスリムは四人までOKだそうだ)、実際誰かが警察に訴えでもしない限り咎められることはないのだろう。日本なら「どっちを取るのよ!」とすごまれるような修羅場必至の場面でも、インドなら「まぁ……どっちもってことで」と丸く(?)収めることも可能なのである。すごいと言えばすごい。
「その旦那さんはよっぽどいい男なんだろうね」
「わからないわ。森林管理の仕事をしている人だけど、それほどハンサムじゃないし」
「もし君が好きになった相手に奥さんがいたらどうする?」
「私だったらそんな人と絶対に結婚しないわ。結婚相手には、誠実で、真面目で、よく働いて、私のことを理解してくれる人がいい。もちろん独身のね」
ショービナはきっぱりと言い切った。至極まっとうな意見だった。
|
|
|
 |
|
|
翌日、ビチヤの町で開かれたお祭り「マライ・メーラ」を見ることができたのも、ショービナのおかげだった。彼女が教えてくれた情報がなかったら、たぶん僕は翌朝早々にこの町を発っていたことだろう。
「この辺り一帯に住む山岳少数部族(アディワシ)たちが集まる大規模なお祭りなの。年に一度しか開かれないから、見逃す手はないわ」
そう彼女は言ったのだが、実際その言葉通りの素晴らしい祭りだった。
祭りの会場には、鮮やかな衣装を着た少数部族の人々が続々と集まっていた。彼らは年に一度のお楽しみのために、バスやトラクターやロバなどを乗り継いで、遠路はるばるやってきたという。
ベガ族はとても見栄えのする部族だった。男性は長髪にターバンを巻き、女性は額に入れ墨を彫り、重そうなアクセサリーで全身を飾っている。ターバンの巻き方には細かい違いがあって、それを見ればどの村に住んでいるかがわかるという。挨拶の仕方も独特で、知り合いに会ったらお互いの足のつま先を触り合うのが習わしだという。
祭りの会場に併設されている市場には、食料や日用雑貨からクワや釜などの農機具まで、およそ生活に必要なもの全てが揃っていたが、ベガ族の女性たちの興味はもっぱらアクセサリー屋に集中していた。銀行口座など持たない人々にとって、財産は着物やアクセサリーに替えて身につけているのが一番安心できるのだろう。
ベガ族の男たちの関心を集めていたのが、牛の首につける「カウベル」だった。この辺りは乾燥していて農作物があまり育たないので、牛の放牧で生計を立てている人が多いのである。
男たちは一番いい音が出るカウベルを買い求めるために、オーディオマニアが高級スピーカーを選ぶときのような真剣な面持ちで、何十個も並べられたカウベルをひとつひとつ「試聴」していた。
「カランコロン」「カランコロン」
僕にはどれも同じような音に聞こえるのだが、彼らにはその違いがわかるようだった。違いがわかる男、ベガ。
ベガ族の牛追いは、たとえ牛の姿が見えなくなっても、カウベルの音だけでその位置を把握することができるという。そのためにもカウベルの音色を聞き分け、それらを覚えておくことが必要なのだ。ちなみにカウベルの値段は一番大きなもので40ルピー(80円)。金属を曲げて溶接してあるだけなので、質はあまり良くなさそうだった。
夕方になると、それぞれの部族の伝統衣装を着た男たちが警察署の前に集まり、踊りをおどり始めた。
アヒール族の男たちは手に持った棒や斧を振り回し、太鼓のリズムに合わせて踊っていた。酔っぱらって足下がふらついている人も多かった。どうやら酒好きの部族らしい。輪の中心では男が大きな角笛を吹き鳴らしていた。100年以上も前に森で仕留められたバイソンの角から作ったのだそうだ。
アヒール族は子安貝の首飾りを何重にも巻いていたので、ステップを踏むたびにジャラジャラという音がした。子安貝はかつて世界各地で貨幣として使われていたものだが、海から500キロ以上も離れたこの土地では、今でも貴重な財産として認知されているようだった。
踊りは次第に激しさを増していった。何十人もの男たちが輪になって、なにものにも邪魔されることなく感情の赴くままに踊り続けた。その興奮の波が踊りの輪を囲んだ群衆にも伝播していくと、人々は次々に地面の砂を掴んで空に投げ始めた。あたりにはもうもうと砂煙が立ちこめ、視界が茶色くかすんでしまう。群衆は輪郭を失って誰が誰だかわからなくなり、その中で太鼓の音とうなり声だけが不自然なほど明瞭に響いていた。それが熱狂のピークだった。
男たちが踊り疲れ、砂煙と興奮が収まってくると、踊りの輪は自然にほどけていった。すると、それぞれの部族の長たちが一人ずつ歩み出てきて警察署の前に集まり、ボールペンで何かの書類にサインを書き始めた。いったい何をしているのだろうか。
「彼らは部族間で争わないことを誓っているんです」
教えてくれたのは、英語を話す若い警察官だった。
「その宣誓と引き替えに、州政府が部族に補助金を出す決まりになっているんです。以前は部族間の争いで死者が出ることも珍しくなかったですからね」
部族間のもめごとに警察は介入しない、というのが州政府の基本方針である。彼らは警察権力が及ばない山奥で、部族の掟を守って暮らしているからだ。しかし部族民もインド国民の一員なのだから、おおっぴらに殺し合いが行われるのを黙って見過ごすわけにはいかない。そんなわけで州政府は平和条約を守ることと引き替えにお金を与え、荒っぽい慣習が残る部族民たちをなんとか懐柔しようとしているのだ。
「インドの山奥にはあなたたち外国人が知らない世界があるんですよ」と警官は言った。
彼の言う通りなのだろう。インドはあまりにも広く、あまりにも深い。
|
|
|
|
|
|
|