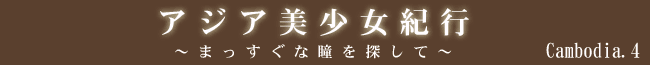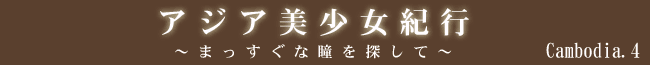|
|
|
|
 |
|
 |
物売り達は十代後半から二十代の女の子ばかりだったが、ボーイフレンドがいる子はほとんどいない。恋愛に関してはまだまだ保守的なのである。リナとその姉妹にも今のところ恋人はいないという。
「姉さんにはいたんだけど、最近別れちゃったのよ」
リナはそう言うと、小さなフォトアルバムを持ってきて僕に渡した。そこには色白でハンサムな若者が写っていた。
「これが姉さんの恋人だった男。顔だけはまぁ悪くないんだけど、性格がひどいの。姉さん以外にもたくさんのガールフレンドがいたらしいの。それがわかったんで別れたの。今までだって何人もの女の子が泣かされてきたのよ。本当に腹が立つわ。今度あいつを見かけたら、このナタで首をちょん切ってやるんだから!」
リナはココナッツを割るための大ぶりのナタを振り上げながら叫んだ。姉のことなのに、まるで自分が裏切られたみたいな勢いである。またそういうことになると実によく喋る。聞いている方もついつい引き込まれてしまう。
|
 |
|
|
|
|
リナは何でも思いついたことを口に出さないと気が済まないタイプの女の子で、「あの日本人のおばさんは私の方を見ようともしない」とか、「あの太ったドイツ人はさんざん値切ったくせに、結局何も買わなかった」といったような仕事の愚痴も隠すことなく聞かせてくれた。リナとしても観光客相手に観光客の悪口を言うなんて機会は滅多にないから、僕との会話を楽しんでいるみたいだった。
「リナは本当によく喋るね」と僕は感心して言った。「君の性格は物売りにぴったりだと思うよ。ほら、モムは静かな女の子だろう? 彼女とは正反対だね」
しかしその言葉を聞いた途端、リナは喋るのを止めて、ぷいとそっぽを向いてしまった。何故かはわからないが、僕の一言が彼女を怒らせてしまったらしい。
リナは良くも悪くも感情がすぐに表情に出てしまう女の子である。お客が売り物を買ってくれたときには愛嬌たっぷりにニコニコと笑っているのだが、客からあからさまに無視されると、頭痛と生理痛と歯痛が一緒にやってきたような表情で店に戻ってくるのだった。そして今はまさにその「不機嫌モード」を全開にして僕を無視しているのである。
|
|
|
|
|
|
僕はリナの機嫌を取るのを諦めて、ほとぼりが冷めるまで近くの村に写真を撮りに出かけることにした。怒りっぽい女の子は忘れるのもまた早い、という経験則を思い出したからだ。しかし夕方になってリナの店に戻ってみても、彼女の怒りはまだ収まってはいなかった。どうやら機嫌を直すのに時間がかかる性格らしい。
「まだ怒っているの?」と僕はリナの背中にそっと声を掛けた。
「誰が怒っているのよ?」
リナはそっぽを向いたまま言った。やっと口を利いてくれたので、僕はほっとした。
「さっきからずっと僕のことを無視してるじゃないか」
「それはね、誰かさんが『リナはよく喋る子だ』なんて言ったから、その誰かさんとは喋らないことに決めたのよ。誰かさんはよく喋る子が嫌いみたいだから」
彼女はいつもの早口でそうまくし立てると、またそっぽを向いた。それを見て、僕は思わず吹き出しそうになった。本当に感情がストレートな子だ。
「それは誤解だよ。リナはよく喋るけど、それが悪いなんて言ってない。ただモムとは違うって言っただけだよ」
「でも、あなたはよく喋る私よりも、あまり喋らないモムのような女の子が好きなんでしょう?」
「そんなことはないよ。君と話しているのは楽しい。だからこうやっていつも話しに来ているんじゃないか」
「嘘よ。みんな『お前は喋りすぎだ』って言うのよ。お前はそこを直さなきゃいけないって」
「そんなことはない。リナの話は面白いよ」
「それに私、日本の女の子みたいに綺麗じゃないもの。売り子をしていたらわかるわよ。日本人はみんな肌が白くて綺麗よ。それに比べて私は醜いわ。みんなそう言うの」
「誰がそんなことを言うの?」
「男友達がそう言うの。それで私傷ついているの」
「君は全然醜くなんてないよ」
僕が見る限り、リナは美人とは言えないけれど、個性的でチャーミングな顔立ちをしている。全然醜くなんてない。
「本当に?」
「本当に」
リナの表情が急に明るくなった。そして上目遣いで僕を見上げた。
「だったら、あたたは私のことを愛してくれるのね? そうでしょ? ドゥー・ユー・ラブ・ミー?」
「アイ・ライク・ユーだよ」
僕は少しうろたえて言った。
「ラブじゃないの?」
「君のことをまだよく知らないからね」
「そんなの関係ないわ。やっぱりあなたも心の中では私を醜いと思っているのね。男なんてみんな嘘つきよ! こうなったらこのナタであなたの喉をちょん切ってやる!」
リナはそう叫ぶと、再び手に持ったナタを大袈裟に振り上げた。僕が慌てて逃げ出すと、「待ちなさい!」と言いながら追いかけてきた。他の売り子達は僕らのやり取りを見て大笑いしている。大騒ぎして気が済んだのか、リナの顔にもようやく笑顔が戻る。
こうして僕らは仲直りの握手をしたのだが、リナは最後まで悪態をつくことを忘れなかった。
「ふん。男なんて大キライ!」
|
|